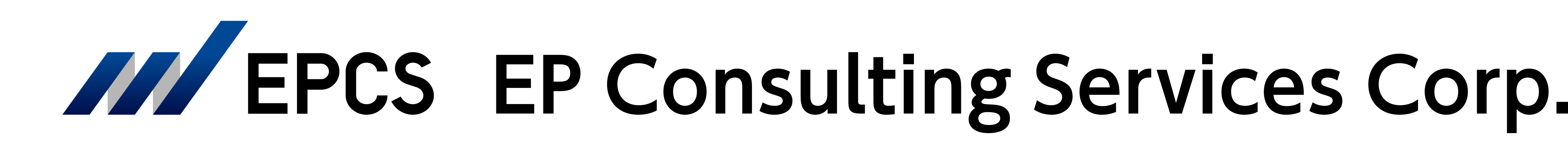Column
Work × Vacation
6月も間もなく終了し、2022年も半年が終了しようとしております。
最近では、気温が30度を超える日もあり、日頃の疲れのみならず、この気温への対応により、いつも以上に疲労が蓄積し、強く疲れを感じている方も多いのではないかと思います。
一方、7月、8月と言えば、夏休み。ここ数年は、コロナ禍の影響で、外出及び旅行を控えていた方が多くいらっしゃるのではないかと思いますが、現状を見てみますと、少しずつではあるものの、人の動きが見られるようになり、仕事と夏休みや年次有給休暇をうまく組み合わせ、久々に充実した休みを取りたいという方が多いのではないかと思います。
そこで、今回は「ワーケーション(Workcation)」について、見て行きたいと思います。
ワーケーション(Workcation)とは
ワーケーション(Workcation)とは、「労働(Work)」と「休暇(Vacation)」を組み合わせた造語となります。観光地やリゾート地でテレワーク(リモートワーク)を活用し、働きながら休暇を取る過ごし方とされており、在宅勤務やレンタルオフィスでのテレワークとは区別されることが多くあります。このワーケーションは、観光庁によって普及促進がなされている「仕事と休暇を組み合わせた滞在型旅行」となり、テレワーク等を活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事をしつつ、自分の時間も過ごすというものです。
また、ブレジャー(Bleisure)という造語もみられ、これは「ビジネス(Business)」と「レジャー(Leisure)」と組み合わせたものとなり、出張先等で滞在を延長するなどして、余暇を楽しむことをいいます。
テレワークにおけるワーケーションの位置づけ
ワーケーションについて「テレワーク(リモートワーク)を活用し」、と言うような記載を複数回させて頂きました。そもそも、ワーケーションは観光庁が推進しているものとなりますので、「働くためのルール」を管轄する厚生労働省の視点では、このワーケーションについて、どのような位置づけになっているのか、見てみたいと思います。
厚生労働省から出ている「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(2021(令和3)年3月25日)」(以下「テレワークガイドライン」という。)内において「テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。」とされています。
そのため、企業がワーケーションを検討する場合、いわゆるテレワークの形態やルールを検討すると言うことになりますので、既にテレワークを導入している企業からすると、1から、新しいものを作るということではありません。
テレワークの形態
ワーケーションは、「情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる」とされています。そこで、テレワークには、どのような形態があるのか、確認してみたいと思います。
テレワークの形態は、①在宅勤務、②サテライトオフィス勤務、③モバイル勤務、の3つに分けられます。
それぞれの内容を見てみますと、①「在宅勤務」は、労働者の自宅で行うものとなり、通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に発生する通勤に要する時間を柔軟に活用できるものとなります。次に②「サテライトオフィス勤務」は、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用することにより、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境が整った場所での就労が可能となるものです。最後に③「モバイル勤務」は、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で業務を行うもので、働く場所を柔軟にすることにより業務の効率化を図るものとなります。
テレワークガイドラインにも記載があるように、ワーケーションは上記②サテライトオフィス勤務と③モバイル勤務に該当することとなります。そのうち、②サテライトオフィス勤務については、自社のオフィスで働くこととなりますので、企業としては③モバイル勤務についてのルールを明確化することが、ワーケーションの導入に対して重要となります。
ワーケーションの導入及び検討にあたって
「ワーケーション(Workcation)」という新しい言葉に惑わされてしまうこともあるかもしれませんが、最終的には、テレワークの形態とルールをしっかりと定めるということになります。
もちろん、ワーケーション独自の論点、例えば、日本以外の海外でも良いのか、場所や通信環境のセキュリティ等も避けては通れません。さらに、導入にあたっては、ルールが既定されている就業規則等、諸規程類や労働契約書の整備のみならず、人事部が直面する労働時間の把握、労災対応、給与計算上の処理等、事前にシミュレーションすべき検討課題は複数あります。
EPコンサルティングサービス及び社会保険労務士法人EOSでは、コロナ禍以降、テレワーク制度の導入、課題解決及び定着のサポート等、数多くの事例と実績を持っておりますので、是非、お声がけ頂ければ幸いでございます。
Yoshito Matsumoto
HR Solution Division/Director and Business Manager Specified Social Insurance and Labor Attorney Social Insurance Labor Consultant Corporation EOS Representative employee Master of Comparative Law, Japan Labor Law Association After graduating from graduate school, he was a consultant at the Tochigi Labor Bureau and worked at a social insurance and labor attorney office in Yokohama, then joined EPCS.