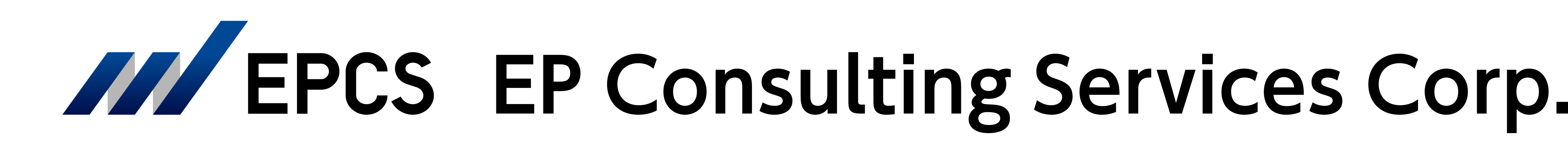Column
有期労働契約のポイント!基本的かつ重要なポイントを解説します
先日、弊社主催セミナー「攻めの人事 × 守りの人事 ~人事制度の再構築と採用支援による「攻めの人事」と法令を遵守した労務管理を行う「守りの人事」へ~」が開催されました。セミナー自体は、想定していた参加者数を超える方々のご来場があり、大盛況と共に無事に終了することができました。
さて、当セミナー第2部の講演の中で、2024年4月から施行される有期労働者の無期転換申込権が発生する契約更新時の労働契約の明示について触れる場面がございました。「無期転換」という言葉自体非常に懐かしく思いながら講演を聞いていたのですが、よくよく考えてみると、定期的に有期労働契約自体や有期労働契約を締結している労働者への対応についてご質問やご相談を受けていることに気づきました。
そこで今回は、有期労働契約の基本的事項について、解説をさせて頂きます。
有期労働契約とは?そしてその上限は?
まず、そもそも「有期労働契約とは?」と言うことになりますが、読んで字のごとく、「有期=期間の定めのある」と言うことですので、「期間の定めのある労働契約」ということになります。
当然のことながら、1週間や1か月、1年、そして5年や10年と期間について労働契約を締結するということになりますが、その期間はどれだけ長くても良いのか、と言うことになりますが、そこは法律が一定の制限を設けています。労働基準法14条を見てみると「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。」と規定されています。
労働契約の種類として、期間の定めのないものと期間の定めのあるもの、そして、期間の定めのある労働契約については、3年(5年)又は一定の事業の完了に必要な期間とされています。
そのため、3年(一定のものにあっては5年)を超える期間を定めた労働契約を締結することは法律に違反することとなってきます。
有期労働契約の基本的な考え方
言うまでもなく、労働契約は会社と労働者の間の契約です。その契約の中で一定期間の労働を約したのが有期労働契約となりますので、
①会社側の視点では、その期間、労働者を雇用しなければならない
②労働者側の視点では、その期間、働かなければならない
ということになり、原則として、労使ともに、一方的に契約を解除することが出来ないものとなります。
もちろん、労使で合意した契約を労使の合意で解約することは可能ですので、有期労働契約を締結した場合、それを解約する方法がない、と言うことではありません。
有期労働者は解雇できない!?
有期労働契約は、その期間の雇用及び労働を約するものであることは先述の通りとなりますが、「じゃぁ、有期労働者を解雇することは出来ないのか?」という話になってきます。 その点については、労働契約法17条に「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と規定されております。
「何だ、解雇できるじゃないか」と言うところかもしれませんが、ポイントは「やむを得ない事由」の有無となります。そもそも使用者が行う一方的な労働契約の解除である解雇が有効であるか否かは「客観的合理性」と「社会的相当性」の観点から判断されることとなります(労働契約法16条)。そして更に「やむを得ない事由」の存在が必要となりますので、有期労働者を解雇するのは、期間の定めのない労働者を解雇する場合よりも難しいと言えるでしょう。
有期労働契約に試用期間!?
有期労働契約の締結に際し、契約当初数カ月間を試用期間とするケースがあります。この理由を聞くと、「試用期間中だったら解雇しやすい」「試用期間中の状況によっては、試用期間の終了と共に契約を辞める可能性がある」というような理由を耳にすることがありますが、前述の通り、契約で締結した期間は雇わなければならず、働かなければならない、そしてやむを得ない事由がないと解雇することは出来ませんので、使用期間終了前後で賃金等の労働条件が変わる場合を除き、有期労働契約に試用期間を設けること自体に余り意味はないかもしれません。
適正な労務管理のために
今回は「有期労働契約」と言う視点で、誤解しやすいポイントを解説させて頂きました。
有期労働契約と言う視点ですと、今回、解説させて頂いたものの他にも、契約更新回数の管理や更新手続き、期間の定めのない労働契約への転換等様々な論点が存在します。
また、冒頭に申し上げました通り、2024年4月からは、無期転換申込権が発生する契約更新時に①就業場所・業務転換の範囲、②無期転換申込機会、③無期転換後の労働条件、を明示しなければならないこととなりました。そして、これらに対応するため、契約書の見直し、就業規則の見直し、無期転換後の労働条件の設定を行う必要が生じてきます。
EPコンサルティングサービス/社会保険労務士法人EOSでは、経験豊富なスタッフが企業の実情に応じたアドバイスを実施しておりますので、是非一度、お声がけ頂ければと思います。
Yoshito Matsumoto
HR Solution Division/Director and Business Manager Specified Social Insurance and Labor Attorney Social Insurance Labor Consultant Corporation EOS Representative employee Master of Comparative Law, Japan Labor Law Association After graduating from graduate school, he was a consultant at the Tochigi Labor Bureau and worked at a social insurance and labor attorney office in Yokohama, then joined EPCS.