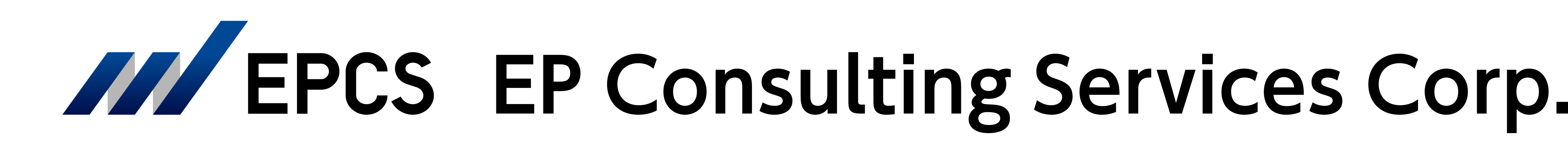Column
週休3日制の光と影
「労働に関する新聞記事やニュースを見たときに、そのニュースの表裏が分かるように、または、何かピンと気づくようになってもらいたい」
これは、私が大学生時代に、初めて労働法という講義を受講した際、第1回目の講義の冒頭で担当教授が受講生に向けて話をした言葉です。近時、「〇〇会社で週休3日制を導入」という見出しや、テレビの該当インタビューで「休みが増える!」「給与が減る・・・。」というような街頭インタビューを見た際、冒頭の言葉を、度々、思い出すことがあります。
そこで、今回は「週休3日制」という働き方の光と影について、見て行きたいと思います。
労働基準法が考える労働時間の枠
1987(昭和62)年の労働基準法改正により、週40時間労働制への動きがスタートし、約35年経過した現在では、週休2日制が多くの企業で定着しています。
労働基準法では、1週間で40時間、1日8時間という法定労働時間を設け(労働基準法32条)、また、毎週1回の休日(労働基準法35条)を義務付けています。
そのため、1週間のうち休日1日を除いた6日間において、1日の上限を8時間として、Total48時間(6日×8時間)のキャンパスに40時間まで労働時間を埋めることが出来るというのが、労働基準法が考える労働時間の枠となります。
上記の労働基準法が想定する考え方とは若干違いますが、多くの企業では、1日8時間という労働時間の上限で5日間働くと40時間、そのため、「7日-5日=2日」という形で、週休2日制が根付いているかと思います。
週休3日制の「光」
次に週休3日制の「光」、いわゆる「メリット」について、見て行きたいと思います。
労働契約は、労使の合意により締結されるものですので、労働者側及び使用者側(会社側)、それぞれの立場で見て行きたいと思います・
まず、労働者側ですが、これは非常に簡単で休日が増えるということではないでしょうか。テレワークで出社日数が減りつつあるとはいえ、勤務日数に変わりはありませんので、勤務日数が減るというのは、労働者にとって1番のメリットではないかと思います。
一方、使用者側(会社側)のメリットとしては、(何らかの変形労働時間制度等を導入しない場合は)労働時間の減少に応じて、賃金を減らし、人件費をカットすることが可能となることかもしれません。もちろん、労働時間の減少に応じ、給与額も減少すれば、それに対する社会保険料も減ることになるかと思います。
もちろん、休日は増やすものの、給与カットを実施せずに、社員のモチベーションアップを図る会社もあるかと思います。
週休3日制の「影」
次に「影」、デメリットです。
労働者側のデメリットとしては、労働時間減少に伴う賃金額の減少、また、1か月単位の変形労働時間制等を導入し週休3日制を実現させる場合には、1日の労働時間の増加が、デメリットとしてあげられると思います。
また、使用者側(企業側)としては、新たな労働時間制度を導入しないのであれば、新たな労働力の確保や業務の見直しを実施し効率化を図ることが必要になるかと思いますし、また、変形労働時間制等を導入するのであれば、制度導入の検討が必須となります。
さらに、場合によっては、所定労働時間が減ったとしても、それをカバーするために残業時間が増えてしまうというケースも出てきてしまうこともあるかと思いますので、適正な業務量の把握とより厳格な労働時間の管理が必要になってくるかと思いますので、人事担当者の育成や増員が必須になってくるかと思います。
最適な労働時間制度の導入にあたって
どのような働き方であれ、全てが労使双方にとって万全なものというのは、なかなかありません。今回は、週休3日制をいうテーマの下、労働時間について触れてみましたが、労働時間制度を見直す場合には、必ず、現状の制度、ビジネス、残業時間等について客観的に把握したうえで、コンプライアンスの視点を持ちながら、自分たちが運用できる制度を検討していく必要があります。
EPコンサルティングサービス及び社会保険労務士法人EOSでは、労働時間制度の現状把握、設計、運用及び定着、そして制度開始の際のサポート等、各種サービスのご提供が可能となりますので、是非、お声がけ頂ければ幸いでございます。
Yoshito Matsumoto
HR Solution Division/Director and Business Manager Specified Social Insurance and Labor Attorney Social Insurance Labor Consultant Corporation EOS Representative employee Master of Comparative Law, Japan Labor Law Association After graduating from graduate school, he was a consultant at the Tochigi Labor Bureau and worked at a social insurance and labor attorney office in Yokohama, then joined EPCS.