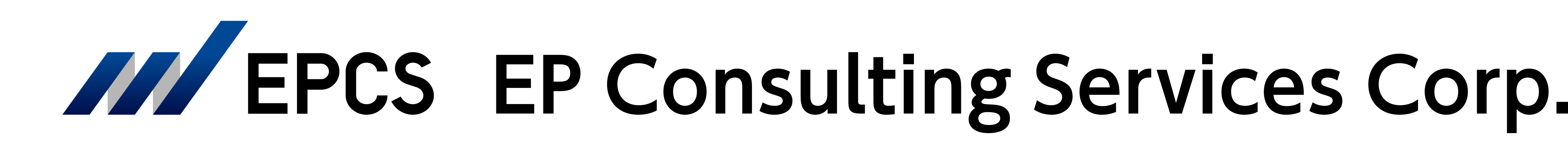Column
職場におけるルール
「働き方改革」。この言葉が一般的に使われるようになってから、3年以上経過しました。働き方改革関連法が施行された2019年当時は、「法改正による働き方改革」として時間外労働の上限規制、年次有給休暇の確実な取得、同一労働同一賃金、というようなものが非常にインパクトの強いものとして注目を浴びていた記憶があります。
一方、現在は、テレワークや週休3日制、兼業・副業というように、働き方の多様性を各企業がそれぞれの視点で検討し、導入するといった「企業主導の働き方改革」のフェーズに移行してきていると感じておりますが、様々な制度を設け、運用していくためには、当然、そこに一定のルールが必要となってきます。
そこで今回は、「職場におけるルール」について、見て行きたいと思います。
基本中の基本「雇用(労働)契約」
職場におけるルール、ということですが、その前提としては「雇用(労働)契約」の存在が必須となります。この「雇用(労働)契約」を締結することにより、企業としては、労働者に対し労務指揮権を持つとともに、労働者が労務に従事したことに対する賃金支払義務を負うこととなります。一方、労働者としては、企業の指揮命令に応じて労務に従事する労働義務を負い、その労働の対価として給与を受ける賃金請求権を持つこととなります。
「雇用(労働)契約」の締結により、企業と労働者の間には上記の基本的な権利義務関係が生ずることになりますが、実際には、雇用契約の締結に伴い、労働者には企業が定めた様々なルールを遵守すべき義務が生じてきます。
職場の憲法「就業規則」
「雇用(労働)契約」の締結により、企業と労働者にはそれぞれ権利義務関係が生じるものの、労働者個々人との個別雇用(労働)契約の中に細かなルールを設定する/記載することは現実的ではありません。そこで、統一的・画一的な職場のルールを定めたものが必要となり、それが職場の憲法ともいわれる「就業規則」となります。
通常、雇用(労働)契約書において「契約書に記載のない事項は就業規則の定めによる」というような一文が記載されているかと思いますが、就業規則には、労働時間、賃金、退職、懲戒、そして服務規定等様々な規定が設けられ、そこに記載された内容は、企業と労働者を共に拘束することとなります。また、労働基準法89条においても、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し、就業規則の作成及び労働基準監督署への届出が罰則付きで義務付けられていることからも、就業規則の重要性を伺い知ることが出来るかと思います
(労働基準法の前身である工場法(明治44(1911)年制定)時は、常時50人以上使用の工場について、就業規則の作成及び届出が義務付けられていました。)。
絶対的な基準「法律」
「雇用(労働)契約」は企業と労働者の間で締結するものであり、「就業規則」は企業が作成し、一定規模以上の企業には労働基準監督署への届出が義務付けられているものです。
この2つのルールを定めるにあたり、当然、その内容については、企業が自由に決められる訳ではなく、労働基準法を代表とする「法律」に定められた基準を満たす必要があります。
当然と言えば当然のことかも知れませんが、近年は、毎年のように何らかの法改正が行われており、その法改正に応じて、就業規則の内容も見直しが必要をなってきます。
見えないルール「労使慣行」
「雇用(労働)契約」、「就業規則」、「法律」。これらのルールは、活字として見える形になっておりますが、どこにも書いていないが、職場のルールになっている事項があれば注意が必要です。これは「労使慣行」といわれます。もし、長期間にわたり、この「労使慣行」が続いている場合、就業規則等にその内容を明示し、職場のルールとして継続していく場合には問題ありませんが、一方で、廃止する場合には、その手順に注意が必要となってきます。
ルール間の優先順位
以上、いくつかのルールを見てきましたが、各ルール間の優先順位について見て行きます(「労使慣行」は、明文化されているものではないので、ここでは除きます。)。
各ルールの優先順位につきましては、労働契約法12条及び13条で規定されており、下記の通りとなります。
法令 > 労働協約(※) > 就業規則 >労働契約
(※)労働協約は、企業と労働組合との間で書面により締結される労働条件等になります。
ルールの遵守及び適正な規定のために
職場におけるルールは、様々なもので規定されており、当然、企業及び労働者双方がしっかりと遵守しなければならないものとなります。各ルールを遵守するためには、その内容を正しく理解することも当然ですが、2重又は3重の解釈が出来ないような、分かりやすい内容になっているかという視点も重要と考えます。
EPコンサルティングサービス及び社会保険労務士法人EOSでは、企業の実態を踏まえ、課題の可視化から解決方法の提案、そしてルール(就業規則)への落し込み及び運用のサポート等、人事の目線におけるサポートの実績を持っておりますので、是非、お声がけ頂ければ幸いでございます。
Yoshito Matsumoto
HR Solution Division/Director and Business Manager Specified Social Insurance and Labor Attorney Social Insurance Labor Consultant Corporation EOS Representative employee Master of Comparative Law, Japan Labor Law Association After graduating from graduate school, he was a consultant at the Tochigi Labor Bureau and worked at a social insurance and labor attorney office in Yokohama, then joined EPCS.