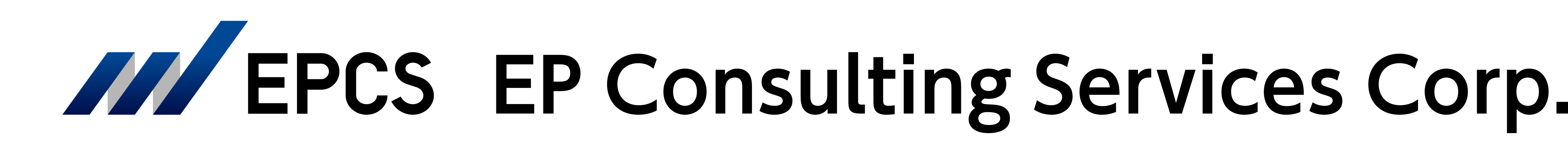Column
労働問題を取り扱う難しさ
4月からスタートした新年度も、早くも1か月が経過します。
3月から4月にかけては、入社、退職そして異動等、人の異動が非常に多く発生する時期であると共にそれに関連し、労使間のトラブルも少なからず発生しているところかと思います。この労使間のトラブル、いわゆる労働問題に対してどう対応するかということに人事を担当される方は、非常に苦労されているのではないかと思います。
そこで以下では、なぜ、労働問題を取り扱うことが難しいのか、触れていきたいと思います。
法律のみを知っていれば良いだけではない-刑事的側面と民事的側面-
労働問題を取り扱う場合には、単純に法律上の規定を確認すれば良いということのみではなく、同様の事例に関する裁判例を確認することが重要となります。
これは、①法律に違反し、懲役や罰則等の刑事罰を受けるか否かという「刑事的側面」と、②労働者が企業を訴えた場合に企業が労働者に対し損害賠償を行う必要があるのか、又は企業が労働者に対して行った行為は正しいものであったのか否かという「民事的側面」の2つの側面を、しっかりと切り分け検討しなければならないことが、労働問題への対応を難しくしているものと思われます。
法律を正しく読み、詳細まで把握可能か-刑事面への対応-
労働に関する法律は労働基準法をはじめ、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等数多く存在しています。当然、法違反を発生させないためには、法律で定められた事項を遵守することが重要となりますが、法律用語及び言葉の使い方を理解したうえで、正しく法律を読み、理解する必要があります。また、労働者派遣法45条のように法律の条文を読むこと自体にストレスを感じるものもありますので、単純に読み理解するといっても、必ずしも簡単ではありません。
また、行政内部の取扱い規定である「通達」の内容も理解しなければ、その条文の本当の意味を理解することが難しくなります。通達は行政内部の取扱い規定であるもの、労働基準監督官が企業に対して調査を行う場合には、その通達も踏まえ確認及び指導することとなりますので、企業としては、法律を正しく読んで理解し、さらに通達で規定されている法律の詳細を把握する必要があります。
判断のポイントを正しく理解できるか-民事面への対応-
つぎに、民事面のポイントとなります。裁判は、地方裁判所、高等裁判所そして最高裁判所という三審制にて実施されているものですが、企業で何らかの労使紛争や労働問題が生じ、裁判となった場合には、裁判所がどのような判断枠組みで判決を行うかということを知り、日ごろの労務管理の中で実施していく必要があります。
判決文を読み、そこに記載されている判断のポイントや言葉の意味、法律の解釈を理解し、日々の労務管理に生かすことは、企業としての大きなリスクヘッジになるとともに、万が一、裁判が提起された場合の結果を想定することが可能となります。
しかし、類似案件や最近の裁判例の判決文を収集するだけでも大きな労力を要すると思いますが、そこから慣れない文章を読み、判決のポイントを押さえるという作業を片手間でやることは非常に困難なものと思われます。
意思決定をサポートする存在として
労働問題を取り扱う難しさは、上記の刑事的側面と民事的側面の両方を考えなければならず、さらに、「人」である従業員としっかりと向き合わなければならないところにあると考えます。人事担当者の方については、労務問題の発生可能性を少しでも低減させるため、是非、従業員とのコミュニケーションに時間を要して頂き、刑事面、民事面の意思決定をサポートする役割として、人事労務のプロフェッショナルファームであるEPコンサルティングサービスを活用して頂ければ幸いでございます。
Yoshito Matsumoto
HR Solution Division/Director and Business Manager Specified Social Insurance and Labor Attorney Social Insurance Labor Consultant Corporation EOS Representative employee Master of Comparative Law, Japan Labor Law Association After graduating from graduate school, he was a consultant at the Tochigi Labor Bureau and worked at a social insurance and labor attorney office in Yokohama, then joined EPCS.