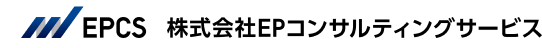コラム
テレワークの勤怠管理完全ガイド!法的義務や管理方法、ルール作りを徹底解説

テレワークにおける従業員の勤怠管理は、労働時間の実態が直接見えないため、従来のオフィス勤務とは異なる難しさが伴います。適切な管理方法がわからず、従業員の自己申告に頼らざるを得ない状況に、課題を感じている方もいるでしょう。
本記事では、テレワークの勤怠管理で生じがちな課題や労働時間把握の法的義務、具体的な管理方法の比較について解説します。担当者が押さえておくべき「中抜け」や残業のルール作りにも触れるので、ぜひ最後までご覧ください。
テレワークの勤怠管理の課題

テレワークを導入した場合、勤怠管理上の課題を生じさせます。ここでは、以下の3つの課題について見ていきましょう。
<テレワークの勤怠管理の課題>
- 労働時間の実態が見えにくい
- 自己申告制の限界と客観性の欠如
- コミュニケーション不足による生産性への懸念
労働時間の実態が見えにくい
テレワークの課題に、従業員の労働時間の実態が物理的に見えにくい点が挙げられます。オフィスであれば、出社・退社時刻や休憩の様子を把握できるものの、在宅勤務ではできません。労働時間とプライベートの境界線が曖昧になりがちです。
従業員が知らないうちに長時間労働に陥る「隠れ残業」のリスクも高まります。一方で、管理者側からは従業員が適切に業務を行っているかが見えにくく、正当な評価が難しいという側面もあります。
自己申告制の限界と客観性の欠如
労働時間の実態が見えにくいことから、テレワークの勤怠管理を従業員からの自己申告に頼っているケースもあるでしょう。しかし、従業員の記憶違いによる申告ミスや、意図的な虚偽申告リスクを完全には排除できません。
客観的な記録に基づかないため、申告された時間が本当に労働時間にあたるのか、企業側の正確な判断は困難です。後述する企業の「労働時間把握義務」を果たす上で課題となり、未払い残業代などを巡る労使間のトラブルに発展する可能性もあります。
コミュニケーション不足による生産性への懸念
勤怠管理は、単に労働時間を記録するだけの作業ではありません。従業員の働きぶりやコンディションを把握し、生産性の維持・向上につなげるという重要な役割も担っています。
テレワーク環境では、オフィスでの雑談や気軽な相談といったコミュニケーションの機会が減少するため、心身の不調を察知したり、業務の進捗遅れに早期に気づいたりするのは困難です。勤怠状況と合わせて従業員のコンディションを把握する仕組みがないと、個々の生産性の低下はもちろん、チーム全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼしかねません。
テレワークでも必要な労働時間の把握

ここでは、テレワーク環境下でも企業に課せられる法的な義務と、怠った場合に生じるリスクについて解説します。
<テレワークでも必要な労働時間の把握>
- 企業の「労働時間把握義務」とは?
- 義務を怠った場合のリスク
企業の「労働時間把握義務」とは?
「労働時間把握義務」とは、労働基準法および労働安全衛生法に基づき、企業(使用者)が従業員の労働時間を客観的な方法で的確に把握しなければならないという法的な義務です。従業員の健康確保や、時間外労働に対する適切な割増賃金の支払いを目的としています。
厚生労働省のガイドラインでは、労働時間の記録は原則として、客観的な記録が求められており、単なる自己申告だけでは不十分です。オフィス勤務かテレワークかという働き方に関わらず、すべての従業員に適用されます。
義務を怠った場合のリスク
企業が労働時間把握義務を適切に果たさなかった場合、経営リスクに直面しかねません。
まず、労働基準監督署による是正勧告や、労働基準法違反として罰則(30万円以下の罰金など)が科される法的リスクがあります。次に、客観的な記録がないため、従業員から未払い残業代を請求されても企業側が反論できず、多額の支払いを命じられる金銭的リスクも高まります。
さらに、労務管理が不十分であるという評判は、従業員のエンゲージメント低下や離職率の増加、採用活動への悪影響につながり、企業の社会的信用を失墜させてしまう場合もあるでしょう。
テレワークの勤怠管理方法を徹底比較

テレワークにおける労働時間を正確に把握するための方法について、以下の代表的な4つの管理方法について比較します。
<テレワークの勤怠管理方法>
- メールやチャットでの報告
- Excelやスプレッドシートでの管理
- VPNやPCのログオン・ログオフ記録
- 勤怠管理システムの導入
メールやチャットでの報告
従業員が始業・終業時や休憩の開始・終了時に、メールやビジネスチャットツール(Slack、Microsoft Teamsなど)を使って上長に報告する方法です。特別なツールが不要でコストをかけずにすぐに始められます。
一方で、従業員の自己申告がベースとなるため、報告漏れや時間の誤記、意図的な虚偽申告のリスクを排除できず、客観性に欠ける点がデメリットです。また、報告内容を管理者が手作業で集計・管理する必要があり、従業員数が増えるほど管理者の負担が大きくなります。
Excelやスプレッドシートでの管理
共有フォルダ上のExcelファイルや、Googleスプレッドシートなどに、従業員自身が始業・終業時刻や休憩時間を入力して管理する方法です。メールやチャットと同様に低コストで導入でき、関数を使えば自動計算できるため、管理がしやすい点がメリットです。
しかし、これも自己申告制であり、客観性の担保や入力ミス、改ざんのリスクといった課題は残ります。法改正に対応したフォーマットの維持管理も自社で行う必要があり、継続的な運用には注意が必要です。
VPNやPCのログオン・ログオフ記録
従業員が使用するPCのログオン・ログオフ時刻や、社内ネットワークに接続するためのVPN(Virtual Private Network)の接続記録を勤怠の記録とする方法です。最大のメリットは、従業員の操作に依存しないため、客観性が高い点です。
ただし、「PCの起動=業務開始」とは限らないため、実態との乖離が生じる可能性があります。また、休憩や中抜けの時間を正確に把握できない点や、PCを使わない業務時間が反映されないといったデメリットがあります。
勤怠管理システムの導入
テレワークに対応した勤怠管理システムは、PCやスマートフォンアプリからワンクリックで打刻でき、IPアドレス制限やGPS機能により不正な打刻も防止できます。最大のメリットは、客観的で正確な労働時間をリアルタイムで、かつ自動的に集計できる点です。
また、法改正にもシステム側が自動で対応してくれるため、コンプライアンスを遵守した労務管理が可能になります。導入コストや月額利用料は発生しますが、長期的に見れば、管理コストや法的リスクの低減といったメリットが上回るでしょう。
テレワークの勤怠管理を成功させる3つのルール作り

ここからは、テレワークの勤怠管理を成功させるための、以下の3つのルール作りについて解説します。
<テレワークの勤怠管理を成功させるルール>
- 「中抜け」のルールを明確にする
- 時間外労働(残業)のルールを徹底する
- コミュニケーションのルールを決める
「中抜け」のルールを明確にする
テレワークでは、育児や介護、役所での手続きといった私用で、一時的に仕事を離れる「中抜け」が発生しやすくなります。ルールが曖昧だと勤怠管理が複雑化しかねません。
そのため、中抜けを認める範囲(例:私用も可とするか)、中抜け時の報告方法(誰に、どう伝えるか)、勤怠の記録方法(勤怠システムで休憩打刻するなど)を就業規則等で明確に定めておく必要があります。
時間外労働(残業)のルールを徹底する
労働時間の実態が見えにくいテレワークは、「隠れ残業」や「サービス残業」の温床となりがちです。従業員の健康を守り、未払い賃金という法的リスクを回避するためには、時間外労働(残業)に関する厳格なルール作りと徹底が不可欠です。
具体的には、残業を原則として「事前申請・上長承認制」とし、申請・承認フローを勤怠管理システムなどを活用して運用しましょう。また、PCの自動シャットダウン機能の導入など、長時間労働を物理的に抑制する仕組みも有効です。
コミュニケーションのルールを決める
テレワークでは、オフィスでの偶発的な会話がなくなるため、意識的にコミュニケーションの機会を設けなければなりません。始業時のオンライン朝礼やチャットの活用など、ルールを明確に設定するといいでしょう。
また、勤怠連絡と合わせて体調や困っていることを報告する欄を設けるなど、勤怠管理をコミュニケーションのきっかけとして活用することも有効です。
まとめ
テレワークにおける勤怠管理は、多様な働き方を推進する上で避けて通れない経営課題です。特に、テレワークであっても企業には「労働時間の客観的な把握義務」が課せられている点に注意しましょう。
対応の基本は、自社の状況に合った勤怠管理方法(勤怠管理システムなど)を選択し、客観的な記録に基づく労働時間の管理です。「中抜け」や「残業」に関する明確なルール整備も大切です。
自社での適切な勤怠管理体制の構築が困難な場合は、EPCSの給与計算・社会保険アウトソーシングをご活用ください。高い専門的知識を持つ担当者が柔軟かつ臨機応変に対応しますので、安心してお任せいただくことができます。