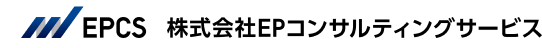コラム
法改正への準備と対応
「労働関係の大きな法改正は3年に1度」。
以前このような言葉を耳にしたことがあります。厚生労働省の大きな役割である、「労働」、「医療」、そして「年金」の3つの政策に関する法改正は順番に巡ってくるということから、冒頭の言葉が生まれて来たものと思います。
さて、私どもがご提供している給与計算、労働・社会保険手続き、人事労務コンサルティングという視点で見てみますと、毎年、何らから法改正が実施され、対応しているところでございます。
そこで今回は、法改正が実施される場合、どのようなことを意識し、準備し、そして対応していくのか、そのフローや考え方について見て行きたいと思います。
全体フロー
法改正が行われる際には、次のようなフローが想定されるかと思います。
①法改正の情報の収集及び確認
②就業規則等法改正に関連する部分の現行ルール(就業規則等)の確認
③現行ルールに照らし合わせ、法改正の影響の有無の検討
④ルール(就業規則等)の変更案の作成及びレビュー
⑤ルール変更
⑥従業員周知(変更内容の説明等)
⑦労働基準監督署への就業規則の届出
如何でしょうか。上記のフローは基本的なものを時系列的に並べたものとなっておりますが、この中で1番重要なものは、②、③になるのではないかと思います。以下では、②及び③について、簡単に触れてみたいと思います。
法改正に関連する部分の現行ルール(就業規則等)の確認
「法改正に関連する部分の現行ルール(就業規則等)の確認」ですが、当然、今回の法改正の内容の把握が出来ていることが前提となるものの、今現在、法改正にかかる部分の自社のルールがどのようになっているのか、しっかりと把握することがポイントとなります。
例えば、「規定すらない」「規定はあるが、実際は運用されていない」「規定と運用ルールがことなる」「規定があること自体を初めて知った」等、様々な反応が出てくるのではないかと思っております。
また、「法改正に関する部分」とはいうものの、現行の規定をみたところ、関連する条文があった場合には、その関連条文に関しても、現行ルールを正しく認識することがスタートになってくるかと思います。
現行ルールへの照らし合わせと法改正の影響の有無の検討
現行ルールの確認及び把握が終了した後は、法改正がもたらす影響の有無及び内容を検討することが必要となります。
多くのケースですと、この部分の検討が疎かになり、法改正により変更したルールの運用がスタートした後に、細々とした問題点が発生してくることがあります。
この影響の有無を検討する際には、
①現行ルールへの影響(就業規則等に規定されている文言の修正等)
②社内手続きや申請書類等の変更の有無
③給与計算や社会保険手続き等、従業員へ直接的に影響のある事項の有無
などを1つひとつ確認及び検討が必要になります。
改正育児・介護休業法への対応
2022年10月1日より、改正育児・介護休業法が施行され、出生時育児休業の創設、育児休業中の就業、育児休業の分割取得、社会保険料免除の変更等が行われます。
この法改正では、新たな制度が出来ることともに、従来の制度が改正されますので、当然のことながら、就業規則の見直しのみならず、社内のプロセス、申請書類、そして、給与計算の際の注意点等を事前に取りまとめておくことが、10月1日以降の業務を円滑に進めるポイントになるかと思います。特に、9月~10月に育児休業を取得される方がいる場合には、法改正の間となりますので、その場合に生じる特有の問題についても整理が必要かと思います(年末調整の時期に近い法改正となりますので、まだ、確認を行われていない場合には、早急に確認が必要かと思います。)。
スムーズかつ漏れのない法改正への準備と対応ために
法改正と言っても様々な法律の改正が行われますので、どの法律がどのように改正されるのかを日常業務の中で、適宜適切に把握することは難しいかと思います。また、法改正の影響の把握や検討といった場合でも、コンプライアンス、企業内人事、従業員といった視点での把握及び検討が必要となります。
EPコンサルティングサービス及び社会保険労務士法人EOSでは、法改正の内容を的確に把握し、企業の現状にあった規定内容の見直し、運用ルールの策定、定着化のサポートを等、様々なサポートの実績を持っておりますので、是非、お声がけ頂ければ幸いでございます。
松本 好人Yoshito Matsumoto
HRソリューション事業部 取締役事業部長 特定社会保険労務士 社会保険労務士法人EOS 代表社員 法学修士、日本労働法学会所属 大学院修了後、栃木労働局での相談業務、横浜の社労士事務所を経て、EPCSに入社。