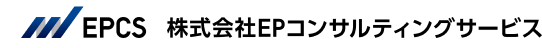コラム
過重労働とは|引き起こされるリスクや対策法も解説します

日常的に労働時間が長くなりがちな企業は、社員の健康状態を守るために過重労働につながらないよう早急に改善・対策を練る必要があります。そこで今回は、過重労働の定義や引き起こされるリスク、原因、防止策について解説します。
過重労働とはいわゆる「働きすぎ」の状態のこと
過重労働とは、身体・精神にダメージを受けるほど時間外労働や休日出勤、出張などが度重なることで、いわゆる「働きすぎ」の状態を指します。
過重労働に法的な定義はありませんが、「時間外・休日労働時間」が月100時間以上または、過去2〜6ヶ月の平均の月80時間を超えた場合に、健康障害のリスクが高まるとされています。
<時間外とは>
- 1日8時間、1週間に40時間を超えた労働
<休日労働とは>
- 労働基準法で定められた「法定」休⽇に労働した時間
過重労働が続くことは、自社の社員にさまざまなリスクを抱えさせることになり、最悪の場合、過労死や過労自殺などの事態にもつながりかねません。
過重労働によって引き起こされるリスク

それでは実際に、過重労働によって社員にどのような悪影響を与える可能性があるのでしょうか。本項目では、過重労働によって引き起こされる可能性がある主なリスクを3つご紹介します。
社員の身体疾患・精神疾患につながる
過重労働は、社員の身体疾患につながり、さまざまな健康障害を引き起こすリスクをもたらします。
<身体疾患の例>
- 心筋梗塞
- 脳卒中
- 胃十二指腸
- 腰痛
- 月経障害
- 過敏性大腸炎
また過重労働は身体的な疾患だけでなく、不規則な生活や業務におけるプレッシャーなどから、精神疾患につながるケースも珍しくありません。
<精神疾患の例>
- うつ病
- 不眠
- 不安障害
実際に業務における強い心理的負荷による精神障害を発病したとする労災請求件数は、年々増加しており、自殺や過労死につながるリスクも高まっています。社員を守るためには、普段から過重労働にならないように業務管理を徹底するなどの対策をとることが大切です。
社内の生産性が低下する
過重労働によって社員の身体状態や精神面が不安定になれば、やる気や集中力の低下につながり、社内全体の生産性が低下する危険性があります。重症化した場合は、休職・退職につながる場合もあり、生産性がさらに低下することで、業績悪化が深刻化することも十分考えられるでしょう。
会社が訴訟されることもある
また社員の身体疾患や精神疾患、過労死、自殺を引き起こしてしまった場合、遺族が企業を訴訟し、多額の損害賠償が発生する場合があります。訴訟されてしまうと、賠償金分の負担が増えるだけでなく、企業のイメージが低下し、今後の人材採用に悪影響を与える事態も懸念されます。
過重労働が起こる3つの原因

過重労働を防ぐためには、原因を把握し事前に対策をとる必要があります。過重労働が起こる主な原因3つを紹介しますので、対策を練る際の参考にしてください。
①人手不足
過重労働が起こる原因として、人手不足により1人あたりの業務が多くなりすぎることが挙げられます。利益を増やすために、人件費を必要最低限に抑えている企業では、社員がどれだけ優秀でも人手不足によって、1人あたりの労働時間が増えて過重労働につながるリスクが高まってしまいます。
②社内の風潮
一部の企業では、「長く働くことを美徳」としている社内の風潮が過重労働の原因になっている場合もあるようです。現在は働き方改革推進などの影響もあり、そのような風潮の企業はなくなりつつありますが、一部の企業では長時間働くことを高評価の対象としているところがあるのです。
長時間労働を評価してしまうと、「ほかの社員が残業しているから帰りづらい」「評価されるために、あえて残業する」といった理由で、過重労働を引き起こす事態につながってしまいます。
③マネジメント不足
社内のマネジメント不足が原因で引き起こされることもあるので、注意が必要です。厚生労働省の「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業」内にある企業調査結果によると、自社で過重労働が起こる原因には以下のものが挙げられています。
<企業における過重労働が起こる原因の調査結果>
- 仕事の繁閑の差が大きいため:42.3%
- 人員が不足しているため:40.5%
- 業務量が多いため:35.2%
このデータを見ても、1年間の仕事量の調整や適切な人員の確保、業務量の割り当てをうまくマネジメントできない場合は、過重労働が起こるリスクが高まると言えるでしょう。
過重労働を防止する5つの対策

過重労働によるさまざまなリスクを回避するために、長時間労働を防止する策を5つご紹介します。
①労働時間を把握する
過重労働を防止するには、普段の自社内の労働時間を把握することが大切です。実際の労働時間がわかったら、労働基準法で定められた基準と比較し、残業時間をどの程度減らさなくてはいけないのかを確認しましょう。労働時間を正確に把握するには、勤怠管理システムを導入するなど工夫をして、普段から徹底して管理することが重要です。
②業務を効率化する
新しいシステムを導入したり、人材の再配置を行ったりして業務を効率化する方法も有効です。業務効率が上がれば、従業員1人あたりの業務量が減るため、過重労働につながるリスクを軽減できるでしょう。
③評価制度を見直す
社内の長時間労働を美徳とする風潮を変えるために、評価制度を見直す方法もあります。評価基準が変われば、就業時間内に仕事を終わらせることが評価につながるという共通認識が生まれ、自然と労働時間が増えすぎることを防げるようになるでしょう。
④ノー残業デーなどを導入する
ノー残業デーなどを導入することも有効な方法です。残業が多くなりがちな多忙な日をあえてノー残業デーに設定することで、過重労働を減らせる可能性が高まります。
少なくてもノー残業デーに設定した日は、周囲の目を気にすることなく帰りやすい雰囲気になるため、不要な残業を減らせる効果も期待できるでしょう。効率良く業務を行うという意識が社員に身につけば、ノー残業デー以外の日の残業も減らせる可能性があります。
⑤有給休暇の取得を促す
企業側が年次有給休暇の取得計画表を作成するなどの対策をして、社員に有給休暇の取得を働きかけることも有効な方法です。有給休暇を従業員に取得させることで、社員の仕事への意欲が高まれば、生産性の向上につながり業務効率が改善する効果が期待できます。労働時間が短縮されたら、過重労働で社員を苦しめる可能性も低くなるでしょう。
まとめ
今回は、日常的に労働時間が長くなりがちな企業の人に向けて、過重労働の定義や引き起こされるリスク、原因、防止策について解説しました。過重労働は、社員の身体疾患・精神疾患につながるだけでなく、社内の生産性が低下するおそれもあります。過重労働によるさまざまなリスクを引き起こさないためにも、業務を効率化したり、普段から労働時間を管理したりするなど対策をとることが大切です。
ただし、いくら対策をとっていても、人員が少ない企業では過重労働は避けられない問題とも言えるでしょう。そこでおすすめしたいのが、アウトソーシングで業務を代行できる「株式会社EPコンサルティングサービス」です。
株式会社EPコンサルティングサービスが提供するアウトソーシングサービスでは、高い専門性を持ったプロフェッショナルチームが人事労務、会計及び経理などの管理業務を支援し、高品質かつスピーディに業務を行います。今回の記事で紹介した対策でも、過重労働の問題が改善する可能性が低い企業の人は、EPコンサルティングサービスに一度お問い合わせください!