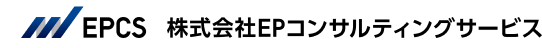コラム
賞与計算の実務ガイド|社会保険料・所得税の計算手順と注意点をわかりやすく解説

企業の経理や人事労務の担当者にとって、賞与(ボーナス)計算は年に数回発生する重要な業務です。毎月の給与計算とは異なるルールや例外的な処理も多く、正確な知識が求められます。
本記事では、賞与計算の基本的な流れから、社会保険料や所得税の具体的な計算方法、担当者が間違いやすいポイントや特殊なケースまで、実務に役立つ情報を解説します。
賞与計算の全体像と基本フロー

賞与計算とは、従業員に支給する賞与の総支給額から、法律に基づいて定められた社会保険料や所得税を控除し、最終的な手取り額(差引支給額)を算出する作業です。基本的な計算フローは以下の通りです。
- 総支給額の確定:就業規則や賃金規程に基づき、個々の従業員の賞与総支給額を決定
- 社会保険料の計算:賞与から控除する「健康保険料」などの社会保険料を算出
- 所得税の計算:総支給額から社会保険料を差し引いた金額を基に所得税を算出
- 手取り額の算出:総支給額から社会保険料と所得税の合計額を差し引き、手取り額を確定
算出された各項目を記載した「賞与明細書」を作成し、従業員へ交付することが所得税法で義務付けられています。
賞与から控除する社会保険料の計算方法
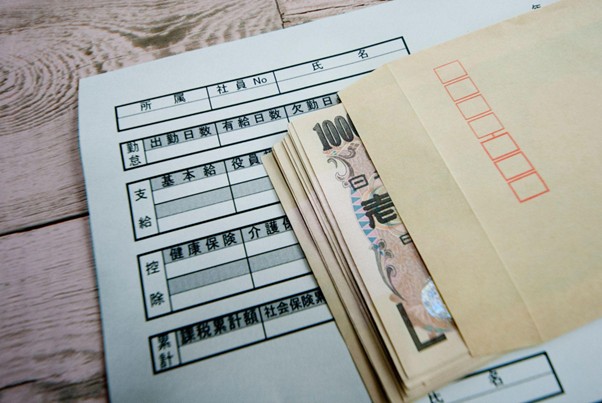
賞与からも毎月の給与と同様に社会保険料が控除されます。ここでは以下の2つのステップで計算方法を見ていきましょう。
<賞与から控除する社会保険料の計算方法>
- 標準賞与額の算出
- 各種社会保険料の計算
標準賞与額の算出
健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の計算には「標準賞与額」という基準額を用います。これは、賞与の総支給額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。
例えば、賞与総支給額が505,500円であれば、標準賞与額は505,000円となります。標準賞与額には以下の上限が設けられており、それを超える分については保険料がかかりません。
- 健康保険・介護保険:年度の累計額が573万円
- 厚生年金保険:1ヶ月あたり150万円
各種社会保険料の計算
標準賞与額が確定したら、それぞれの保険料率を乗じて保険料を算出します。健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は、会社と従業員で半分ずつ負担(労使折半)します。
- 健康保険料=標準賞与額×健康保険料率(※)÷2
- 介護保険料=標準賞与額×介護保険料率÷2
- 厚生年金保険料=標準賞与額×厚生年金保険料率(※)÷2
※健康保険料率は、会社が加入している健康保険組合や、所在地の都道府県(協会けんぽの場合)によって異なる。
40歳以上65歳未満の従業員が対象。料率は全国一律で、定期的に改定される。
※厚生年金保険料率は現在18.3%で固定
雇用保険料の計算方法

雇用保険料の計算は、他の社会保険料と異なり、標準賞与額ではなく賞与の総支給額をそのまま用います。
- 雇用保険料=賞与総支給額×雇用保険料率(労働者負担分)
雇用保険料率は毎年見直されるため、厚生労働省の発表する最新の料率を確認してください。
所得税(源泉徴収税額)の計算方法

所得税の計算は、賞与計算の中でも特に複雑で間違いやすいポイントです。以下の手順に沿って解説します。
<所得税(源泉徴収税額)の計算方法>
- 課税対象額を求める
- 前月の給与データを確認する
- 扶養親族の数を確認する
- 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率を確認する
- 所得税額を算出する
課税対象額を求める
所得税を計算するための基礎となる「課税対象額」を算出します。課税対象額を求める式は以下のとおりです。
- 課税対象額=賞与総支給額-社会保険料の合計額
前月の給与データを確認する
次に、賞与支給月の前月の給与データを確認します。具体的には、前月の総支給額から社会保険料を差し引いた金額が必要です。 この金額が、所得税率を決定するための基準となります。
扶養親族の数を確認する
従業員から提出されている「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づき、扶養親族の数を確認します。この申告書を提出しているかどうか(甲欄・乙欄の別)と扶養親族の人数によって、適用される税率が変わるからです。
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率を確認する
国税庁が毎年発行している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用します。まず、表の縦軸で「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」がどの範囲に該当するかを探します。
次に、表の横軸で「扶養親族等の数」を確認し、両者が交差する欄に記載されている率が、賞与にかかる所得税の税率(源泉徴収税率)です。
所得税額を算出する
最後に、算出した課税対象額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
- 所得税額=課税対象額×源泉徴収税率
モデルケースで賞与の手取り額を計算してみよう

ここではモデルケースを使って、賞与の手取り額を計算します。前提条件は以下のとおりです。
- 従業員:35歳、東京都在住(協会けんぽ加入)、扶養親族1人
- 賞与総支給額:500,000円
- 前月の給与(社会保険料控除後):300,000円
- 健康保険料率:9.98%(令和6年度・東京都)、厚生年金保険料率:18.3%、雇用保険料率(労働者負担):0.6% ※いずれも仮の料率
- 社会保険料の計算
- 所得税の計算
- 手取り額の計算
標準賞与額:500,000円
健康保険料:500,000円×9.98%÷2=24,950円
厚生年金保険料:500,000円×18.3%÷2=45,750円
雇用保険料:500,000円×0.6%=3,000円
社会保険料合計:24,950円+45,750円+3,000円=73,700円
課税対象額:500,000円-73,700円=426,300円
税率の確認:「前月給与30万円」「扶養1人」の条件で「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を確認すると、税率は8.168%(仮)
所得税額:426,300円×8.168%=34,820円(1円未満切り捨て)
手取り額:500,000円-73,700円-34,820円=391,480円
賞与計算で迷わないためのQ&A

ここでは、賞与計算でよくある疑問についてお答えします。
<賞与計算で迷わないためのQ&A>
- 賞与の支給月に退職する従業員の社会保険料はどうなりますか?
- 産休・育休中の従業員への賞与の扱いは?
- 休職等で前月の給与がゼロの場合、所得税はどう計算しますか?
賞与の支給月に退職する従業員の社会保険料はどうなりますか?
社会保険料は、「資格喪失日の前月分」まで徴収されます。資格喪失日は退職日の翌日です。
月末退職の場合は、資格喪失日が翌月1日になるため、退職月分の社会保険料が徴収されます。賞与からも通常通り社会保険料は控除されます。月の途中で退職した場合は、資格喪失日が退職月内にあるため、退職月分の社会保険料は徴収されません。したがって、賞与から社会保険料(健康保険・厚生年金)を控除する必要はありません。
産休・育休中の従業員への賞与の扱いは?
産前産後休業や育児休業の期間中は、事前に会社経由で年金事務所へ「産前産後休業取得者申出書」または「育児休業等取得者申出書」を提出することで、社会保険料(健康保険・厚生年金)が被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。 この免除は賞与にも適用されます。ただし、連続して1ヵ月超の育児休業(出生児育児休業も含む)の取得が必要です。
ただし、賞与にかかる社会保険料が免除されるためには、「その賞与が支給された月の末日に育児休業等を取得していること」などの条件があります。 なお、雇用保険料と所得税は免除の対象外です。
休職等で前月の給与がゼロの場合、所得税はどう計算しますか?
前月の給与支払いが無い場合、通常の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は使えません。 代わりに、以下の手順で計算します。
- (賞与の総支給額-社会保険料)÷6 を計算
- 扶養親族の数に応じて「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を算出
- 上記で求めた税額を6倍した金額が、賞与から源泉徴収する所得税額となる
まとめ
賞与計算は、社会保険料と所得税の計算ルールを正確に理解することが不可欠です。特に、毎月の給与計算とは異なる「標準賞与額」の概念や、所得税計算で「前月の給与」を参照する点が重要なポイントです。また、退職や産休・育休、休職といった個別のケースにも対応できるよう、例外的な処理方法をあらかじめ把握しておけば、ミスを防ぎ、スムーズな実務が可能となるでしょう。
自社での賞与計算が困難な場合は、EPCSの給与計算・社会保険アウトソーシングをご活用ください。高い専門的知識を持つ担当者が柔軟かつ臨機応変に対応しますので、安心してお任せいただくことができます。