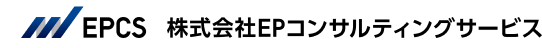コラム
2023年度法改正!上期の振返りとこれからの準備等を解説します
2023年度も半分が経過致します。今年度も様々な法改正が行われ、各社対応に追われたことと思いますが、如何でしたでしょうか。対応出来ている、実は不完全等、対応状況は各社違っているのではないかと思います。
そこで今回は、2023年度上期に行われた法改正等について振り返ると共に、2023年度下期の法改正や2024年度の法改正対応に向けて準備しておくべき事項等を解説させて頂きます。
2023年度上期の法改正
まず、2023年度上期の主たる法改正をピックアップ致しますと、下記のようなものが挙げられます。
①労働基準法
中小企業に対する割増賃金率の適用猶予措置の廃止
②労働基準法
デジタルマネーの開始
③育児・介護休業法
育児休業の取得状況の公表
④雇用保険法
雇用保険料率の変更
⑤労災保険法
精神疾患の労災認定基準の改正
上記①から⑤の中においても、もっともインパクトの大きかったものとしては、「①労働基準法:中小企業に対する割増賃金率の適用猶予措置の廃止」だったかと思います。これまでは、月の時間外労働が60時間以上の場合、大企業のみに50%以上の割増賃金の支払いが義務付けられていましたが、今年度からは中小企業においても、その対応が必要となりました。これに伴い、給与計算システムや勤怠システムの改修、就業規則の改訂等の対応を行われたのではないかと思います。
しかしながら、4月以降、60時間を超える時間外労働が発生していない企業においては、改修が問題なく行われているか確認出来ていないケースもあるかと思いますので、今後、発生したときは、注意して確認をする必要があります。
2023年度下期の法改正
2023年度下期につきまして、現状、企業の労務管理に大きな影響を与える法改正はございません。
その中で、1つ注意が必要となるものとしては、10月1日以降に改定が実施される地域別最低賃金額の変更となります。金額改定のタイミングにつきましては、都道府県によって若干の差はありますが、今回の改訂により、全国加重平均が初めて1,000円を超えることとなりました。
この改訂に伴い、各従業員の給与額が最低賃金額を下回っていないか否かを確認することはもちろんのこと、固定残業代を導入している企業におきましては、固定残業代の見直しも必要になってくるかと思いますので、是非一度、確認をしてみてください。
2024年度の法改正に向けた準備
2023年度下期は、上記最低賃金の確認のみならず、2024年度の法改正に向けた準備も必要となってきます。2024年度に予定されている法改正は、以下の通りとなります。
①労働基準法
労働条件明示事項の追加
有期労働契約締結後の変更及び更新の際の説明事項の追加
専門業務型裁量労働制における本人からの同意取得
②職業安定法
求人募集時に就業場所・業務の変更の範囲、有期労働契約の更新上限条項の追加
③障害者雇用促進法
障害者法定雇用率の引上げ
④健康保険法・厚生年金保険法
短時間労働者への適用拡大
⑤確定拠出年金法
DCの拠出限度額見直し
そして、施行日については、①から③は、2024年4月、④は2024年10月、そして⑤については2024年12月となっております。
これらの法改正のうち、「①労働基準法:労働条件明示事項の追加」につきましては、2024年4月以降の入社に備え、下期に現状の労働契約書・労働条件通知書の確認及び見直しが必要となります。今回の法改正で追加となる事項は、「通算契約期間又は更新回数の上限」、「就業場所」、「業務変更の範囲」となります。
労働条件の明示は、入社後の労使トラブルの事前防止にはかかせない非常に重要なものとなりますので、労働契約書・労働条件通知書の見直しを下期に実施すべき事項として管理し、確実に実施して頂ければと思います。
法改正への適切な対応のために
以上、今回は「2023年度の法改正」と「2024年度に向けた準備」について触れさせて頂きました。
近年、労働・社会保険関係の法改正は毎年実施されており、企業では、日々その対応に追われていることが容易に想像できます。1つの法改正が様々なところに影響する可能性は少なくありません。そのため、法改正が行われる場合には、どこに対して影響があるのかのみならず、それに関連する業務の全体を把握し対応方法を検討することで、工数の増加を最小限に抑えられるのではないかと思います。
EPコンサルティングサービス/社会保険労務士法人EOSでは、経験豊富なスタッフが企業の実情に応じたアドバイスを実施しておりますので、是非一度、お声がけ頂ければと思います。
松本 好人Yoshito Matsumoto
HRソリューション事業部 取締役事業部長 特定社会保険労務士 社会保険労務士法人EOS 代表社員 法学修士、日本労働法学会所属 大学院修了後、栃木労働局での相談業務、横浜の社労士事務所を経て、EPCSに入社。