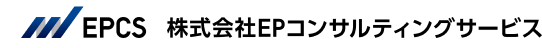コラム
給与支払に関する正しい知識と思い込み
給与支給日になると自分の銀行口座に給与が振り込まれている。
まだ、現金で給与を支給している企業もあるかもしれませんが、ある意味、銀行口座に給与が振り込まれることは、当然のことと思われているかと思います(余談ですが、私も以前は、現金で給与を貰っていたことがあります。)。
そして、2023(令和5)年4月から、給与のデジタルマネー(いわゆる、〇〇ペイによる給与の支払い)がスタートしますが、それに先立ち、厚生労働省は昨年11月末頃、2つの通達を発出しています。
今回は、この通達をきっかけとした、給与の支払に関するコラムとなります。
「給与デジタル払い」と検索すると…
現在、「給与デジタル払い」、「給与 デジタルマネー」というような言葉をインターネットで検索すると、「給与のデジタルマネー払いをする場合、労使協定の締結と本人の同意が必要です」というような記事に辿り着くことがあります。
確かに、冒頭に記載した11月末頃に厚生労働省が発出した通達「賃金の口座振込み等について(令4.11.28基発1128第4号)」を読んでもそのようなことが書いてあります。
しかし、その通達をよく見ると、「口座振込み等を行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録による協定を締結すること」と記載されており、労使協定の締結が義務付けられています。
「口座振込み等を行う事業場」「労使協定」???
給与を従業員の銀行口座に振り込むために、入社の際、通行のコピーや銀行口座を記載した書面等を提出させている企業がほとんどだと思います。そして、この行為は、労働基準法施行規則第7条の2に規定される「労働者の同意を得た場合」を充足するものであり、これをもって、従業員給与を本人の銀行口座へ振り込むことが法律上、正しく行われていると思われています。
そうです。「思われている、思い込まれている」だけです。先ほどの通達に「口座振込み等を行う事業場」と記載があり、この「口座振込み等」という言葉については、「預貯金口座への賃金の振込み、証券総合口座への賃金の払込み又は資金移 動業者口座への賃金の資金移動(以下「口座振込み等」という。)」と通達内に記載があります。
つまり、今回のデジタルマネー払いに限らず、銀行口座への給与の支払いを実施するためには、労働者に対しては同意を得る必要があると共に、会社は過半数組合又は労働者過半数代表者との労使協定の締結が必要となります。
新たな労使協定!?
この口座振込みに関する労使協定について、今回、新たに締結を求められるものなのか、それとも従来から存在していたものなのか。もし、新たな労使協定であれば、現金での給与支給をしていない全国の企業に労使協定の締結を求めていることになります。
この「口座振込みに関する労使協定」について、調べたところ、実は25年前の「賃金の口座振込み等について(平10.9.10基発530号)」、そして、更に遡ること23年前の「賃金の口座振込み(昭50.2.25基発112号)」に、労使協定の締結に関する記載がありました。つまり、約50年以上前から労使協定の締結は求められていたものの、殆ど、知られていない労使協定となっています。実は、今回の通達に基づき、口座振込みに関する労使協定について複数の労働基準監督署に問い合わせを行ったところ、「本人の同意があればそれだけで問題ありません」、「今回から締結して下さい」又は「ちょっと確認します」と言うように、行政内部においてもその存在感が非常に薄いことを実感しました。
では、どうする!?
厚生労働省が発出した「賃金の口座振込み等について(令4.11.28基発1128第4号)」において、デジタルマネーによる支払いを実施しる場合のみならず、口座振り込みを実施する場合には、労使協定の締結が必要であることが、改めて、明確になりました。
一方、現在、口座振込みを実施している企業であっても、この労使協定を締結していない企業は数多くあるかと思います。
通達は、行政内部の指示であるものの、実際はこの通達に基づき、労働基準監督官は各企業に対し指導を実施することとなります。今回のようなケースでは、法律上、労使協定の締結が求められていないものの、通達において労使協定の締結を求めていることから、法違反に対し行われる是正勧告ではなく、法違反になる恐れがある場合に実施される指導票の交付が行われる可能性は否めません。つまり、このような指導が行われるリスクがあることから、労使協定の締結を、是非、実施してください。
思い込みの排除と正しい理解に基づく労務管理のために
今回、新たな通達の発出により、本来の正しい手続きが非常に明確になりました。
人事労務の仕事に限らず、複数回又は複数年、同じ業務を繰り返していると、「以前は〇〇だったから」や「〇〇だろう」というような思い込みによる対応が増え、結果として、誤った処理を実施しているケースが見られます。
EPコンサルティングサービス及び社会保険労務士法人EOSでは、法改正等の内容やその影響をしっかりと把握し、企業及び人事担当者が実施すべき対応や決定をサポートしておりますので、気になることがありましたら、お気軽にお声がけ頂きたいと思います。
松本 好人Yoshito Matsumoto
HRソリューション事業部 取締役事業部長 特定社会保険労務士 社会保険労務士法人EOS 代表社員 法学修士、日本労働法学会所属 大学院修了後、栃木労働局での相談業務、横浜の社労士事務所を経て、EPCSに入社。