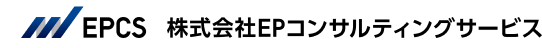コラム
4月から育児休業法が改正されます
改正育児休業法の概要
今回は、間近に迫った育児・介護休業法の改正(特に育児休業法について)をテーマに取り上げます。
この4月から育児休業法が変わる、という情報をご存知の方は多いと思いますが、少し詳しく説明すると、「令和3年6月9日に公布(成立した法律を発表)された改正育児介護休業法の中に、令和4年4月1日から施行(法律の効力が発動)されるものが含まれる」と言う事ができます。
つまり、全ての法改正内容がこの4月から一度に施行されるのではなく、段階的に発効されていくことになります。
主だった改正内容(関連法を含む)のアウトライン及び施行日は次の通りです。
【令和4年4月1日施行】
妊娠・出産に関する個別の周知と意向確認の義務化:社員又はその配偶者が妊娠・出産することを会社に申し出た際は、育児休業の制度などを個別に周知して育児休業取得の意向を確認することが義務化されます。
有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和:現行法では、有期雇用労働者が育児休業を取得できる要件の一つに「引き続き雇用された期間が1年以上」というものがありますが、これが撤廃されます。(ただし、労使協定を締結することにより本要件を継続することもできます)
【令和4年10月1日施行】
出生時育児休業の創設:現行法における、いわゆるパパ休暇(子の出生後8週間以内に父親である社員が育休を取得した場合は、それとは別に育児休業を取得できる)が、出生時育児休業に改変されます。子の出生後8週間以内に、通算4週(28日)の出生時育児休業を、2回に分割して取得することができるようになります。
育児休業の分割取得:現行法では、子が1歳(最長で2歳まで延長可)に達する日までに原則として1回に限り取得できますが、改正法により、2回に分割して取得することができるようになります。
※ 出生時育児休業と育児休業を合わせると、最大で4回に分けて育児休業を取得することができるようになるので、男性の育児休業取得促進策の色合いが濃いものとなっています。
出生時育児休業給付金の創設(雇用保険法):出生時育児休業制度の導入に対応する形で、雇用保険の雇用継続給付の種類が増えます。
育児休業中の保険料の免除要件の見直し(健康保険法・厚生年金法):育児休業期間中の社会保険料免除の要件が変わります。
≪拡大するもの≫
「育休開始日」と「終了日の翌日」のそれぞれの属する月が異ならないと免除月が発生しなかったところ、それぞれの属する月が同じであっても、休業日数が2週間以上であれば、その月の社保料が免除されるようになります。
(月末を含んでいなくても、月内に2週間以上育児休業を取得した場合、当該月の社会保険料は免除になる)
≪縮小するもの≫
月次の保険料が免除される月(その月の末日に休業している)は、賞与に対する保険料が免除されますが、現行要件に「休業期間が1か月を超えること」が加わります。
【令和5年4月1日施行】
育児休業取得状況の公表:常時雇用する労働者の数が1,000名を超える事業主は、毎年育児休業の取得状況を公表することが義務化されます。
賞与保険料免除の要件拡大
さて、盛りだくさんの改正内容が控えていますが、個人的に「育児休業中の保険料免除の縮小」に注目しています。
現状は、例えば6月に賞与が支払われる会社の社員が、6月30日に一日だけ育児休業を取得した場合でも、6月分の保険料(給与と賞与分)が免除されます。
こういった運用は、想定されていた育児休業の取得目的からは外れるかもしれませんが、「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」という健康保険法第159条の規定を上手く解釈し、利用したものではないでしょうか。
しかし、政府の社会保障審議会では、これは「法の抜け穴」であり「公平性に欠ける」ので適正化したほうが良い、という話し合いが行われたようで、今回の法改正の一部に含まれるに至りました。
私見ですが、そこまで大きなインパクトはないと思いますので、節約術としてあえて残しておくくらいの余裕を見せて欲しかったところではありますが、社会保障制度を維持するためであれば仕方ないのかもしれません。
日本と海外の医療比較
日本の社会保障制度、特に健康保険制度は諸外国と比較しても非常に行き届いたものとなっております。
例えば、盲腸(虫垂炎)にかかり手術が必要になった時のことを考えてみましょう。
開腹手術が行われる時は1週間程度の入院が必要となりますが、健康保険では3割の自己負担となりますので、一般的には、手術費用として10万円程度、入院治療費で約14万円、併せて24万円ほどかかると言われております。
さらに、高額療養費制度を利用できますので、平均的な所得の被保険者であれば、1か月の医療費の上限が8万円程度に抑えられます。
これがアメリカの場合だとどうなるでしょうか。
アメリカにおいて公的医療保険制度は、高齢者と障害者そして低所得者を対象としたものに限られています。つまり、対象とならない人達は民間の医療保険に入らざるを得ませんが、高額な保険料を支払えず無保険状態の人が増加しています。
アメリカで盲腸手術を受けて55,000ドルの請求を受けた、という事例は、決して特殊なケースではありませんので、何百万円もの医療費の支払いができずに自己破産してしまうことが、深刻な社会問題となっているのが実情です。
またイギリスでは、公的医療機関(National Health Service)において無料で診療を受けることができますが、待ち時間が長いうえに医師のレベルにバラツキが多いため、きちんとした診療を受けたい人は私立病院に行くそうですが、盲腸で入院した場合の医療費は100万円前後かかると言われています。
日本に話を戻しますと、世界の中で最も病院数の多い国であり、医療技術はトップクラスを誇ります。そのサービスを、(保険料の負担は決して小さくありませんが)比較的に安価で享受できることは、安心して日々の生活を送ることができる、正にセイフティネットと言えるのではないでしょうか。
ただし、病院にお世話になる機会が少ないに越したことはありませんので、健康的な生活を心がけたいものです。
私は、週一回のペースでのスポーツジム通いを約5年間続けているのですが、始めてから風邪をひくことがめったになくなりました。高熱が出たのは、コロナワクチンの2回目くらいです。やはり、体を動かすことが健康に良いことは間違いありませんので、ぜひ皆さんにも、継続的な運動を生活に取り入れることをお勧め致します。
高まる男性の育児休業取得率
さて、今回は、育児休業の法改正についてご説明させていただきましたが、改正目的の一つとなる「男性の育休取得促進」は、社会的な動きとなりつつありますので、男性が育児休業を取得することが珍しくない日が来るかもしれません。
いざそうなった時に、慌てるようなことにならないためにも、代替要員を確保する方策を検討して関連する費用について予算を計上しておく、などの準備(想定)をしっかりしておくことが肝要と考えます。
今回は、以上となります。
皆様の中でも多いと思いますが、弊社は3月で年度が終わります。
心機一転して4月からの新年度に臨みたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
加瀬 光紀Mitsunori Kase
社会保険労務士法人EOS 代表社員 HRソリューション事業部 マネージャー 2006年入社。2000年の社労士試験合格後、柏の社労士事務所や事業会社の人事部門にて職歴を積む。入社後はHRチームの立ち上げに携わり、2010年に社労士法人EOSの代表社員に就任。立ち上げたBPO/業務改善プロジェクトの総数は100件を超える。