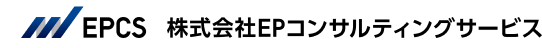コラム
労働衛生の三管理
梅雨も明け、7月も間もなく終了するとともに夏本番を迎えようとしています。今年は、「猛暑」「熱中症注意」という言葉を耳にすると共に、「健康管理」「体調管理」という言葉も耳にします。
「〇〇管理」という言葉を人事労務のワードで連想すると「労務管理」、「労働時間管理」、「有休管理」という言葉には触れることも多いかと思いますが、余り聞きなれない言葉ですと「労働衛生の三管理」というものがあります。「労働衛生」という言葉が付いているので、労働基準法又は労働安全衛生法に関連するものではないかと、イメージはつくかも知れません。しかし、その中身というと、この言葉だけでは分かりづらいのではないかと思います。
そこで今回は、「安全衛生の三管理」について、そもそも、どのような管理を指しているのか、そして、その概要について、簡単に触れてみたいと思います。
「安全衛生の三管理」とは
まず初めに、「安全衛生の三管理」には、どのようなものが含まれているのか見て行きたいと思います。
「安全衛生の三管理」は、労働安全衛生法に規定される、①作業環境管理、②作業管理、③健康管理、の総称を言い、それぞれの概要は、以下の通りとなります。
①作業環境管理 … 作業環境の有害要因を排除するなど、作業環境を良好な状態に維持すること
②作業管理 … 作業に伴う個々の労働者の疲労やストレスが過度にならないように作業を適切に管理すること
③健康管理 … 労働者の健康状態を的確に把握し、必要な措置を講ずること
以下では、それぞれの管理の中身について、その概要を見て行きたいと思います。
作業環境管理
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場などの政令で定める一定の作業場について、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない(労働安全衛生法65条)とされています。作業環境測定を行わなければならない作業場としては、鉱物性粉じんを著しく発散する屋内作業場などが政令で定められており、測定すべき対象及び測定の回数については、各規則の中で定められています。
作業環境測定は、職場環境の状況を的確に把握するために実施されますが、ただ単に実施されるだけでは意味がないため、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するために必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない(労働安全衛生法65条の2)とされています。
作業管理
次に作業管理です。この作業管理については、事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない(労働安全衛生法65条の3)とされています。
この作業管理は、1988(昭和63)年の法改正で規定されたものとなり、具体的には、一連続作業時間と休憩時間の適正化、作業量の適正化が含まれており(昭和63.9.15基発601号の2)、また、電通事件(最二小判平12.3.24)では、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷などが過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なうという危険」が発生するのを防止することを目的とするものとも述べられていますので、非常に重要な管理であることが伺われます。
健康管理
労働衛生の三管理の最後は、「健康管理」になります。
皆さんの身近なところで言うと健康診断は、この健康管理に含まれることとなります。労働安全衛生法では、雇入時検診、配置替え時検診、定期健診、離職後検診など様々な健康診断が定められております。当然、法定の基準に基づき健康診断を実施することは必要となりますが、健康診断実施後の措置をしっかりと実施しなければ意味がありません。また、健康診断実施後の措置として、労働時間の短縮等を実施する場合もあるかと思います。その場合、現場の責任者のところに一定の健康情報が行かざるを得ない場合にあるかと思いますが、健康情報は非常にセンシティブなものとなりますので、その取扱いには、十分に注意が必要となります。
職場における労働者の健康
以上、今回は「労働衛生の三管理」について触れさせて頂きました。
労働安全衛生法は、労働基準法とともに「労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進すること」と目的としております。
コロナ禍以降テレワークの浸透により、出社自体が減っている会社様も多くあるのではないかと思いますが、今一度、「快適な職場環境」が形成されているか否か、状況を確認し、可能なところから1つひとつ職場環境の維持改善を行ってみてはいかがでしょうか。
松本 好人Yoshito Matsumoto
HRソリューション事業部 取締役事業部長 特定社会保険労務士 社会保険労務士法人EOS 代表社員 法学修士、日本労働法学会所属 大学院修了後、栃木労働局での相談業務、横浜の社労士事務所を経て、EPCSに入社。