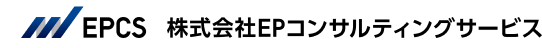コラム
月次決算早期化のメリットとは?遅れる理由や経理DXの進め方を徹底解説
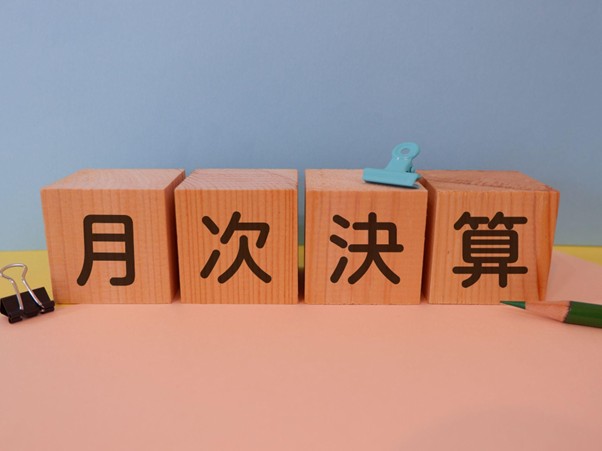
企業の経営状況をリアルタイムで把握するには、月次決算の早期化が不可欠です。ただし、「何から手をつければいいのかわからない」と悩む担当者も少なくありません。
本記事では、月次決算の基本や早期化がもたらすメリット、決算が遅れてしまう具体的な理由を解説します。月次決算早期化を目指している方は最後までご覧ください。
月次決算とは
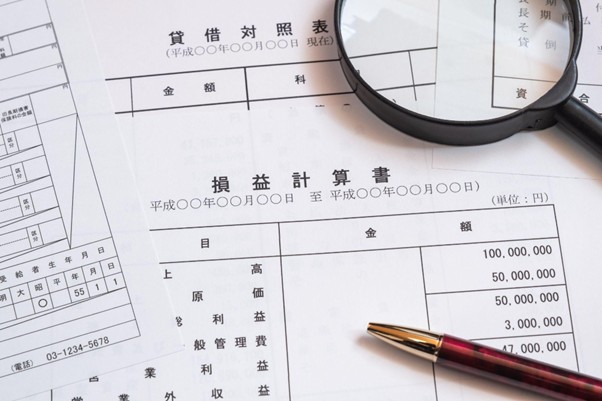
月次決算とは、1ヶ月ごとに行う決算業務です。 法律で義務付けられている年次決算とは異なり、月次決算の実施は各企業の任意に委ねられています。
年次決算が1年間の経営成績を確定させるものであるのに対し、月次決算は月単位での損益や財産の状況把握が目的です。経営者はタイムリーに自社の経営状況を数字で把握できるため、迅速な意思決定につながります。
作成される書類に厳密な決まりはないものの、一般的には損益計算書や貸借対照表、資金繰り表などが作成され、経営陣への報告に用いられます。
月次決算の早期化がもたらす3つのメリット

実際に月次決算の早期化がもたらす3つのメリットについて見ていきましょう。
<月次決算の早期化がもたらすメリット>
- 迅速で的確な経営判断につながる
- 年次決算の負担が削減できる
- 金融機関からの信頼性が向上する
迅速で的確な経営判断につながる
月次決算の早期化による最大のメリットは、経営判断のスピードと精度向上です。
例えば、ある商品の売上が予測を大幅に上回った場合、月次決算が早期に完了していれば、即座に増産や追加の仕入れといった次のアクションを検討できます。 反対に、業績が悪化している部門や予期せぬコスト増が発生した場合も、問題を早期に発見し、傷口が浅いうちに対策を講じることが可能です。
変化の激しい現代の市場において、この「スピード」は企業の競争力を左右する重要な要素となるでしょう。
年次決算の負担が削減できる
月次決算によって、毎月の業務が増えるように思うかもしれませんが、年次決算の負担を軽減する効果が期待できます。年に一度、1年分の膨大な伝票や帳簿を整理し、決算書を作成するのは大きな労力を要します。 月次決算を毎月行っていれば、期末の作業集中が避けられ、業務を平準化可能です。月次で会計処理のミスや漏れをチェックする機会が生まれるため、年次決算の土壇場で大きな手戻りが発生するリスクも低減できます。
金融機関からの信頼性が向上する
月次決算を早期に行い、常に最新の経営状況を提示できる体制にしておけば、金融機関からの信頼性向上につながります。金融機関が融資を判断する際には、企業の財務状況が厳しく審査されます。直近の業績がわかる月次決算資料をすぐに提出できれば、審査もスムーズに進みやすくなるでしょう。 定期的に財務情報を提供しているという事実は、経営の透明性を示すアピールとなり、有利な融資条件につながるかもしれません。 決算の遅れは、企業体質への疑念を抱かせる要因になりうるため、適切な月次決算は効果的です。
月次決算が遅れる3つの理由

月次決算の早期化を目指す企業も多いなか、実現に苦労している声も耳にします。ここでは、月次決算が遅れる理由を3つ見ていきましょう。
<月次決算が遅れる理由>
- アナログな情報収集
- 手作業による入力と確認
- 部門間の連携不足
アナログな情報収集
月次決算が遅れる原因のひとつが、情報収集のアナログな手法です。 請求書や納品書、経費精算の申請書などが紙媒体でやり取りされている場合、各部署から経理部門に情報が集まるまでに多くの時間を要します。
担当者が出張で不在にしていたり、書類が他の郵便物に紛れてしまったりと、物理的な制約もボトルネックになります。 情報がそれぞれの部署で個別に管理されていると、全体の数値を集計するだけでも手間と時間がかかりかねません。
手作業による入力と確認
収集した情報を会計システムへ入力する工程も、遅延の原因となりがちです。何百枚もの請求書や伝票の内容を目で確認し、手で入力する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーを誘発します。
ミスが発覚すれば、確認と修正にさらに時間がかかり、悪循環に陥りかねません。Excelなど複数のツールを併用している場合、データの転記作業が発生し、非効率とミスの温床になります。 昔ながらの紙の振替伝票を起票する慣習が根強く残っている企業も少なくありません。
部門間の連携不足
月次決算は経理部門だけの業務ではなく、全社的な協力体制が不可欠であるため、部門間の連携が不足していると、スムーズな進行は望めません。営業部門からの売上報告が遅れたり、経費精算の締め切りが守られなかったりすると、経理部門の作業はそこでストップしてしまいます。
特定のベテラン社員しか業務の進め方がわからないといった「業務の属人化」も深刻な問題です。 担当者が不在の場合、業務が完全に滞ってしまうリスクを抱えることになります。
経理DXによる月次決算早期化のステップ

月次決算を早期化するための強力な武器となるのが経理DXです。ここでは、経理DXを推進するための具体的な3つのステップを紹介します。
<経理DXによる月次決算早期化のステップ>
- 証憑の収集・管理の電子化
- 仕訳入力と残高確認の自動化
- レポート作成と共有の効率化
証憑の収集・管理の電子化
最初のステップは、紙でやり取りされている請求書や領収書といった証憑(しょうひょう)の電子化です。電子請求書発行システムを導入すれば、取引先との書類のやり取りがデータ上で完結し、郵送やファイリングの手間がなくなります。経費精算システムを導入すれば、従業員はスマートフォンで撮影した領収書の写真を使って、いつでもどこでも経費の申請が可能になります。経理部門は紙の原本の到着を待つ必要がなくなり、データ収集の時間を大幅に短縮可能です。
仕訳入力と残高確認の自動化
次のステップは、会計システムやRPAツールなどを活用した定型業務の自動化です。AI-OCR(光学的文字認識)機能を備えたシステムを使えば、受け取った請求書データを自動で読み取り、会計システムに仕訳データとして取り込めます。販売管理システムや給与計算システムなど、社内の様々なシステムを連携させれば、データを手作業で転記する必要がなくなり、リアルタイムでの残高確認が可能になります。入力ミスを防ぎつつ、担当者は単純作業から解放されるでしょう。
レポート作成と共有の効率化
最後のステップは、経営判断に必要なレポートの作成と共有の効率化です。BI(ビジネスインテリジェンス)ツールなどを活用すれば、会計システムに蓄積されたデータを自動で集計・分析し、経営状況を可視化するダッシュボードやレポートをリアルタイムで作成可能です。
月次決算が完了するのを待つまでもなく、日次や週次の単位で業績の進捗をモニタリング可能になります。 経理担当者がExcelでデータを加工してレポートを作成する手間が省けるだけでなく、経営陣はいつでも最新のデータに基づいた意思決定を行えるようになります。
経理DXの導入を成功させるポイント

最後に経理DXの導入を成功させるポイントを3つ見ていきましょう。
<経理DXの導入を成功させるポイント>
- 社内ルールの整備・周知する
- 小さく始めて成功体験を積む
- 現場の理解と協力を得る
社内ルールの整備・周知する
DXを推進するにあたり、社内の業務フローやルールを見直しましょう。「経費精算は月末までに申請を完了させる」「請求書は全てシステム経由で発行する」といった明確なルールを定め、全社的に周知徹底しなければなりません。経理DXは経理部門だけの改革ではなく、全社を巻き込んだプロジェクトであるという認識を経営層が持ち、リーダーシップを発揮することが成功の鍵となります。
小さく初めて成功体験を積む
いきなり全社的に大規模なシステムを導入しようとすると、現場の抵抗が大きくなったり、予期せぬトラブルが発生したりするリスクがあります。まずは、ペーパーレス化しやすい請求書発行業務や、導入効果の分かりやすい経費精算システムなど、特定の領域に絞ってスモールスタートを切るのがおすすめです。 小さな成功体験を積み重ね、そのメリットを社内で共有すれば、他の部門の協力も得やすくなるでしょう。
現場の理解と協力を得る
新しいシステムの導入は、現場の従業員にとって業務の進め方が変わることを意味し、一時的に負担が増える場合もあります。なぜDXが必要なのか、それによってどのようなメリットが生まれるのか(例:単純作業の削減、残業時間の短縮など)を丁寧に説明し、現場の理解と協力を得ることが不可欠です。従業員のITスキルに合わせた研修を実施したり、操作が簡単なツールを選んだりするなど、現場に寄り添った導入支援がDXをスムーズに定着させるポイントになります。
まとめ
月次決算の早期化は、迅速な経営判断や年次決算の負担軽減、金融機関からの信頼性向上といった、企業の競争力を高めるうえで欠かせない多くのメリットをもたらします。実現を妨げているアナログな業務フローや属人化といった課題は、経理DXの推進により解決可能です。
自社で月次決算が実現できない場合は、EPコンサルティングサービス(EPCS)の経理・会計・税務アウトソーシングをご活用ください。高い専門性を持ったプロフェッショナルチームが高品質かつスピーディにサービスを提供いたします。