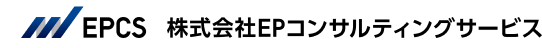コラム
償却資産とは|償却資産申告書の提出や計算方法についても分かりやすく解説

償却資産は登記に記載されないため、毎年1月1日に所有状況を示した償却資産申告書を管轄の自治体に提出する必要があります。しかし、償却資産や償却資産申告書はあまり知られていないため、取り扱いに困っている企業の人も多いでしょう。
そこで今回は、償却資産の特徴や償却資産申告書の提出方法、償却資産税の計算方法について分かりやすく解説します。本記事を読めば、償却資産を所有している場合に必要な手続きの方法が分かるので、ぜひ参考にしてください。
償却資産とは?

償却資産とは、土地や家屋を除いた、事業のために使用する資産全般を指します。土地や家屋には固定資産税が課せられますが、償却資産には償却資産税が課せられます。
償却資産に該当する資産は以下のとおりです。
<償却資産の対象>
- 構築物:塀、門、塗装路面、庭園、看板
- 建物付属設備:簡易物置、予備電源設備、野外の照明設備
- 機械及び装置:建設機械、製造設備の機械装置
- 船舶:遊覧船、釣船、ボート
- 航空機:ヘリコプター、飛行機
- 車両及び運搬具:大型特殊自動車
- 工具、器具及び備品:パソコン、自動販売機、医療機器、美容機器
土地や建物は登記で所有状況を確認できますが、償却資産の所有状況を確認するには専用の申告書を提出する必要があります。
償却資産ではない資産
償却資産に該当するかどうか判断がつきづらい場合もあります。もし償却資産に該当するにも関わらず、償却資産でないと誤認してしまった場合は都税事務所や県税事務所などから指摘される可能性があるので気をつけましょう。
償却資産ではない資産は以下のとおりです。
<償却資産ではない資産>
- 土地、家屋
- 自動車、バイク
- 無形固定資産・繰延資産
- 棚卸資産、絵画、美術品
- 家屋と構造上一体となる建物付属設備
基本的に償却資産税以外の税金が発生する資産は、償却資産の対象から外れると判断して良いでしょう。たとえば、固定資産税が課税される土地や家屋、自動車税等が課税される自動車やバイクなどは償却資産には含まれません。重複して課税されないように、償却資産に該当するかどうか明確にしておくことが大切です。
償却資産に含まれる建物付属設備
償却資産の対象として「建物付属設備」を挙げましたが、すべての設備が該当するわけではない点に注意が必要です。償却資産に該当するかどうかは、家屋と建物付属設備の所有者が同一かそうでないかで基準が異なります。
家屋と建物付属設備の所有者が異なる場合、賃借人が取り付けた事業用の建物付属設備はすべて償却資産として取り扱うことになるためシンプルで分かりやすいです。しかし、家屋と建物付属設備の所有者が同じ場合は、償却資産の判断方法が少し難しいです。
家屋と建物付属設備の所有者が同一の場合は、以下の条件を満たせば償却資産として取り扱われます。
<家屋と建物付属設備の所有者が同じ場合>
- 家屋から独立している設備
- 事業用に供される設備
これら以外の「家屋と一体型構造の設備」や「家屋の効用を高めるだけの設備」は家屋の一部とみなされるため、償却資産税ではなく固定資産税が課せられる点に注意しましょう。たとえばエアコンは天井埋め込み型の場合、建物に付属していると言えますが、取り外しできるものについては家屋から独立していると判断できるため、償却資産に含まれるケースもあるのです。
償却資産申告書とは?

償却資産申告書とは、固定資産税や償却資産税を適切に計算するために、償却資産の所有状況を管轄の自治体へ報告する書類を指します。登記にある土地や家屋は報告不要ですが、記載がない償却資産は償却資産申告書を提出して報告しなければなりません。
償却資産申告書の提出期限
償却資産申告書の提出期限は、毎年1月31日と定められています。また、償却資産申告書には1月1日時点の償却資産の所有状況を記載する必要があります。申告書の作成が完成したら、償却資産の所在する管轄の自治体へ提出するのが一般的です。
登録と公示が行われる
提出した償却資産申告書や調査内容をもとに償却資産の価格などが決められ、課税台帳に登録されます。登録後に公示が行われると、所有者は課税台帳の内容を確認できます。万が一、登録内容に不服がある場合は審査を申し出ることも可能です。
納税通知書と納付書が送られてくる
償却資産では、自治体から送られてくる納税通知書と納付書を使って償却資産税を納める必要があります。なぜなら、自治体が算出した金額を納税者に通知してから支払う「賦課課税方式」という仕組みを採用しているからです。一般的に年4回納税通知書と納付書が届きます。
償却資産税の計算方法

償却資産税の計算方法も確認しておきましょう。
<償却資産税の計算式>
- 償却資産税額=課税標準額×税率
※課税標準額は100円未満切り捨て
税率は自治体によって異なりますが、一般的に1.4%の場合が多いです。ただし、税率を1.5%と定めている自治体もあるので、事前に確認してから算出することが大切です。
償却資産税の免税点
償却資産税には免税点が設定されており、評価額(課税標準額)が合計で150万円未満であれば課税されません。たとえば購入時には150万円以上の評価額で課税対象だった場合でも、償却後には課税標準額が減少して150万円未満になった場合には、償却資産税が発生しません。
20万円未満の償却資産の特例
20万円未満の償却資産では、特例として全額損金算入または3年で均等償却することが認められています。償却資産は、資産の種類ごとに耐用年数が設定されており、通常使用期間の経過によって費用計上します。たとえば、耐用年数が6年の自動車の場合は、通常6年間にわたって費用として計上します。
ただし、自動車の取得価額が20万円未満の償却資産であれば、6年ではなく3年で均等償却することも可能です。大きい金額を費用として計上できる方が支払う税金が少なくなるため、3年で均等償却するのがベターでしょう。
つまり20万円未満の償却資産は特例の適用によって、より大きな金額を費用計上できるので節税効果を期待できます。
まとめ
今回は、償却資産の特徴や償却資産申告書の提出方法、償却資産税の計算方法について解説しました。償却資産とは、土地や家屋を除いた、事業のために使用する資産全般を指します。土地や家屋だけでなく、自動車、バイクなど償却資産に該当しない資産も数多くあるため、重複して課税されないよう対象に含まれるかどうかを明確にしておくことが大切です。
また償却資産を所有している場合は、毎年1月31日までに管轄の自治体へ償却資産申告書を提出する義務があることにも気をつけましょう。「所有している資産が償却資産に該当するのか分からない」「償却資産申告書の作成が難しい」といった場合には、「株式会社EPコンサルティングサービス」にご相談ください。
株式会社EPコンサルティングサービスが提供するプロフェッショナルアウトソーシングでは、高い専門性を持ったチームが償却資産を含むあらゆる資産の管理業務をサポートいたします。償却資産の取り扱いにお困りの際は、ぜひ株式会社EPコンサルティングサービスにお問い合わせください。