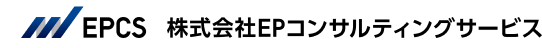コラム
インボイスで簡易課税はどう変わる?知らないと損する2割特例との比較と注意点

インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入以降、「簡易課税制度はどうなるの?」「2割特例とは何?どちらが得なの?」といった疑問を抱える方は少なくないでしょう。
本記事では、インボイス制度導入後の簡易課税制度の扱いや、新たに設けられた「2割特例」について詳しく解説します。基本から具体的な計算方法、どちらの制度を選択すべきかという判断ポイントまでわかりやすく説明します。
インボイス制度導入後の簡易課税制度とは
まずはインボイス制度導入後の簡易課税制度について、以下の2つの視点で詳しく見ていきましょう。
<インボイス制度導入後の簡易課税制度>
- 簡易課税制度の基本
- インボイス制度導入による簡易課税制度への影響
簡易課税制度の基本
簡易課税制度は、中小事業者の消費税の納税事務負担を軽減するための制度です。この制度では、課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出することで選択できます。
最大の特徴は、仕入れにかかる消費税額を実際に計算する代わりに、売上にかかる消費税額に事業の種類に応じた「みなし仕入率」を乗じて計算する点です。みなし仕入率は事業の種類によって異なり、卸売業は90%、小売業は80%などと定められています。
これにより仕入税額の計算やインボイスの集計・保存の事務負担が軽減されます。一方で、実際の仕入税額がみなし仕入率で計算した金額より多い場合でも、その差額は控除できない点には注意しなければなりません。
インボイス制度導入による簡易課税制度への影響
インボイス制度導入後も簡易課税制度は引き続き適用可能です。インボイスの有無に関わらず、売上にかかる消費税額にみなし仕入率を乗じて計算すればよく、インボイスを保存しておく必要はありません。
ただし、簡易課税制度を選択していても、取引先からインボイスの交付を求められれば、適格請求書発行事業者の登録は必要となります。その場合は、発行したインボイスの写しを保管する必要があります。
「2割特例」とはどんな制度?

次に、インボイス制度の開始に伴い新しく設けられた「2割特例」に関して見ていきましょう。
<2割特例>
- 2割特例が生まれた背景と目的
- 2割特例の対象者と適用期間
- 2割特例の具体的な計算方法
- 2割特例のメリット・デメリット
2割特例が生まれた背景と目的
2割特例は、インボイス制度を機に課税事業者に転換する免税事業者が、急激な税負担や事務負担の増加に直面することを緩和する目的で導入されました。これまで消費税の納税義務がなかった事業者が、インボイス発行のために課税事業者になると、消費税の申告・納税が必要となり、経理処理も複雑になります。こうした変化に対する激変緩和措置として、期間限定で設けられた特例措置です。
2割特例の対象者と適用期間
2割特例は、インボイス制度開始を機に免税事業者から課税事業者になった方が対象です。具体的には、適格請求書発行事業者の登録により課税事業者になる場合や、課税事業者選択届出書を提出して登録する場合が該当します。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス発行のために課税事業者になったケースが主な対象です。元々課税事業者である場合や、課税期間短縮特例の適用を受けている場合は対象外である点に注意しましょう。
適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
2割特例の具体的な計算方法
2割特例の具体的な計算方法は以下のとおりです。
納付税額=売上にかかる消費税額×20%
例えば、課税売上が550万円(うち消費税額50万円)の場合、納付税額は「50万円×20%=10万円」となります。これは、実質的にみなし仕入率を80%として計算するのと同じ効果があります。
2割特例のメリット・デメリット
2割特例には、計算の簡単さや事務負担の軽減、事前の届出不要といった点がメリットです。特に、サービス業や飲食店業など、簡易課税制度のみなし仕入率が80%未満の業種では、簡易課税よりも納税額が少なくなる可能性があります。
一方、令和8年9月30日までの期間限定であることや、実際の仕入れが多くても控除が売上税額の8割に固定されること、卸売業などみなし仕入率が80%を超える業種では簡易課税制度の方が有利になることがデメリットとして挙げられます。
「簡易課税」vs「2割特例」どっちを選ぶべき?

インボイス発行のために課税事業者になった方は、簡易課税と2割特例のどちらを選ぶべきでしょうか。以下の3つの視点で解説します。
<簡易課税と2割特例の比較>
- 納税額の比較シミュレーション
- 事務負担の比較
- 選択のポイントと注意点
納税額の比較シミュレーション
課税売上高500万円(消費税額50万円)の場合、事業の種類によって簡易課税と2割特例のどちらが有利か異なります。
卸売業(みなし仕入率90%)は簡易課税が有利、小売業(みなし仕入率80%)は同額、製造業・建設業(70%)、飲食店業(60%)、サービス業(50%)、不動産業(40%)は2割特例が有利となります。
つまり、みなし仕入率が80%未満の事業は2割特例、80%の事業は同額、90%の事業は簡易課税が有利です。
事務負担の比較
2割特例の場合、売上にかかる消費税額さえ集計できれば、あとは20%を乗じるだけで税額が算出できます。インボイスの保存・集計は不要であるため、事務負担も軽いです。
一方で、簡易課税制度の場合は、売上を事業の種類ごとに区分し、それぞれのみなし仕入率を適用して計算しなければなりません。複数の事業を行っている場合は、その区分作業が発生します。帳簿への記載は必要ですが、インボイスの保存・集計は不要です。
事務負担の軽減を最優先するならば、2割特例の方が優れています。
選択のポイントと注意点
簡易課税と2割特例のいずれを選ぶかは、事業区分に応じたみなし仕入率と2割特例の比較がポイントです。人員や使用できるソフトの状況も確認したうえで、有利な制度を選択しましょう。
ただし、2割特例は期間限定であることや、簡易課税制度は事前の届出が必要であり、原則2年間継続適用となる点にも注意して、選択する必要があります。
手続きと実務上の注意点
各制度の手続きと実務上の注意点について解説します。
<手続きと実務上の注意点>
- 簡易課税制度を選択・継続する場合の手続きと注意点
- 2割特例を利用する場合の手続きと注意点
簡易課税制度を選択・継続する場合の手続きと注意点
簡易課税制度の選択には、「消費税簡易課税制度選択届出書」を原則として適用を受けたい課税期間の開始前日までに税務署に提出しなければなりません。インボイス発行事業者になるために免税事業者から課税事業者になった場合は、登録日の属する課税期間中に提出すれば、その期間から簡易課税が適用されます。
また、原則2年間の継続適用が必要である点には注意しなければなりません。そして、自社の事業がどの「みなし仕入率」の区分に該当するかを正確に判定し、複数の事業を行っている場合はそれぞれの売上を区分して計算しましょう。さらに、仕入税額控除の要件として、帳簿に必要な事項を記載し保存すべき点にも注意が必要です。
2割特例を利用する場合の手続きと注意点
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方が対象であり、事前の届出は不要です。消費税の確定申告書にその旨を付記し、申告・納付することで適用を受けられます。
適用期間が令和5年10月1日から令和8年9月30日までの各課税期間である点には注意が必要です。また、簡易課税制度選択届出書を提出済みでも2割特例を選択できます。特例の適用をやめた後も簡易課税制度を再選択する際の届出は不要です。申告ごとに2割特例の適用が選択できる点も忘れないようにしましょう。
まとめ
インボイス制度導入後に設けられた2割特例の影響もあり、消費税の納税方法や事務処理で新たな対応を迫られているケースもあるでしょう。間違った選択をすると、多めに消費税を払うことになりかねません。本記事の内容を参考に、簡易課税制度と2割特例を理解し、損をしない形で納税しましょう。
どの制度を利用すればいいかわからない場合は、EPコンサルティングサービス(EPCS)の経理・会計・税務アウトソーシングをご活用ください。貴社に最適な制度選択を、税理士法人EOSが提案いたします。