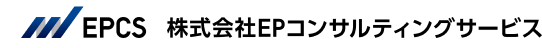コラム
評価について
最近転職サイトのCMがとても多いと思うのは私だけでしょうか。そんなに誘わないでくれ、というのが正直な思いだが、転職を決意する理由として、会社の評価に対する不満が多く、自分に対する会社の評価に納得がいかなければ、もっと自分を高く買ってくれる会社に転職したいと思うのは当然のことでもあるので、こればかりは仕方がないとも思っている。ただ1つ気になることがある。「評価」というものの違いについてである。
CMでは「あなたのスキルを高く評価してくれる」と誘っていて、今の会社で評価されないスタッフから見れば、これはとても魅力的な文句なのだが、自分を高く評価してくれない今の会社の評価と、スキルを高く評価してくれる転職候補の会社の評価は、本質的に全く異なるものだということに気づいていない人もいるのではないだろうか。
内部の評価は、その人の実際の仕事ぶりを評価する。これに対して、転職サイトで言っている「評価」は職務経歴書に書かれた内容を本人の自己申告に基づいて評価しているだけで、実質的な評価ではなく表面的な評価である。Aという業務をスムーズにこなしたか、周りに助けてもらいながらやっとの思いでこなしたかは職務経歴書ではわからない。ただ、Aという業務を経験しているのなら、こういうこともできるのではないかと自分たちの業務内容に合わせて評価しているだけである。もし本人が、本当はほぼ上司にやってもらっただけなのに、自分でやったと申告した場合の評価は正しい評価にはならないが、それが外部からの評価の限界である。採用担当者としては、本人の自己申告が本当かどうかを見極めるしかない。
EPCSでは1年に1度、自己評価と上司による評価を行ったうえで面談を行っているが、可能な限り公平な評価になるよう、様々な工夫をしている。業務ごとに異なる上司と仕事をするので、評価も複数の人間が行うことにより、一人の評価ですべてが決まるということは起こりえない。評価項目も多岐にわたり、会計や税務の知識だけでなく、社内及び社外のコミュニケーション力、作業の効率性、正確性等色々な評価項目で評価を行い、スタッフそれぞれの強みと弱みをそれぞれ評価できるように考えている。それでももちろん完璧な評価を行うことはできないので不満を持つスタッフがいるのも事実であるが、なるべくスタッフの声を聴き、毎年評価のやり方についても検討してアップデートしている。
自分の評価が気になるのは当然のことであり、それが必ずしも自己評価と一致しないのもまたよくあることである。会社としては、それがすぐに転職理由になるのではなく、冷静に評価を受け止め、自分に足りないところを把握し、改善のための意欲を持ってもらうことが重要である。そのためには納得できるような丁寧な説明と、改善のためのサポートを手厚くすること、また常にあなたが会社にとってとても大切な存在だということを伝えることも大切と考えている。
小杉 晃世Teruyo Kosugi
ACCTソリューション事業部 マネージャー 2005年EPコンサルティングサービスに入社。外資系事業会社やSPCを中心に担当